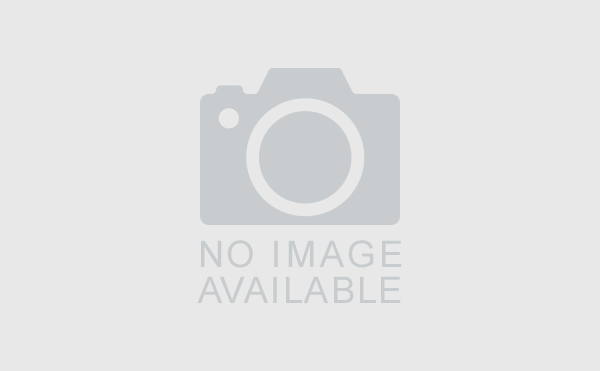【2026年行政書士法改正】特定技能の書類作成、登録支援機関に任せると違法?
特定技能の書類作成、
登録支援機関に「丸投げ」していませんか?
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。
施行から1ヶ月——当事務所には、かつてないペースで相談が寄せられています。
こうした声が、施行後わずか1ヶ月で急増しています。
本記事では、施行後の現場で実際に起きていることを踏まえ、受入企業・登録支援機関がいま取るべき対策を解説します。
2026年1月1日
行政書士法改正 施行済
違反者には「1年以下の拘禁刑」または「100万円以下の罰金」
両罰規定により法人にも最大100万円の罰金
📌 この記事の結論
登録支援機関が特定技能の書類を作成するのは違法。
受入企業は「行政書士に直接依頼」が必須です。
登録支援機関の役割は「支援」であり「書類作成」ではありません。「支援費用に含まれている」「無料でやっている」「行政書士を雇っている」——どんな言い訳も通用しなくなりました。
❓ こんな状況に心当たりはありませんか?
一つでも当てはまる方は、この記事を最後までお読みください。
施行から1ヶ月——現場で起きていること
行政書士法の改正施行から約1ヶ月が経過しました。当事務所の実感として、大きく2つの変化が起きています。
変化①:登録支援機関からの「外注先探し」が急増
施行前は「うちは大丈夫」と様子見だった登録支援機関が、施行を機に一斉に行政書士への外注先を探し始めています。
当事務所にも「これまで自社で書類作成をしていたが、行政書士に依頼する体制に切り替えたい」という相談が施行後、目に見えて増加しました。実際に、継続的にお仕事をいただいている登録支援機関も複数あります。
変化②:受入企業からの「体制見直し」相談
登録支援機関だけでなく、受入企業からの相談も増えています。特に多いのが「自社支援に切り替えたい」という内容です。
これまで登録支援機関に支援を委託し、書類作成も含めて丸投げしていた企業が、行政書士法改正を機に「支援は自社で行い、書類作成だけ行政書士に直接依頼する」という体制への移行を検討し始めています。
💡 ここがポイント
登録支援機関・受入企業ともに「体制の見直し」はすでに始まっています。先行して対応した企業・機関ほど、スムーズな移行と安定した事業継続を実現できます。
なぜ登録支援機関の書類作成は「違法」なのか
結論から言います。特定技能の在留資格申請書類を作成できるのは、行政書士(または弁護士)だけです。これは行政書士法で明確に定められており、登録支援機関が行うことは法律違反です。
行政書士法が定める「業務独占」
📜 行政書士法 第1条の2(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
特定技能に関する以下の書類は、すべて「官公署(出入国在留管理局)に提出する書類」です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格変更許可申請書
- 在留期間更新許可申請書
- 1号特定技能外国人支援計画書
📜 行政書士法 第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
⚠️ つまり、こういうことです
登録支援機関が、受入企業や外国人から依頼を受けて、報酬を得て、特定技能の申請書類を作成すること——これは行政書士法第19条に違反する違法行為です。
「支援業務の一環」「サービスの一部」「無料でやっている」——どんな名目であっても、実質的に報酬を得ている限り、違法性は変わりません。
登録支援機関の「本来の役割」とは
登録支援機関は、入管法に基づいて設置された機関です。その役割は「1号特定技能外国人支援計画」の実施であり、在留資格申請の代行ではありません。
✅ できること
- ✓ 支援計画の「実施」
- ✓ 事前ガイダンスの実施
- ✓ 出入国時の送迎
- ✓ 住居確保・生活支援
- ✓ 日本語学習機会の提供
- ✓ 相談・苦情対応
- ✓ 申請書類の「取次」(持参のみ)
❌ できないこと
- ✗ 在留資格申請書類の「作成」
- ✗ 支援計画書の「作成」
- ✗ 届出書類の「作成」
- ✗ 申請に関するコンサルティング(有償)
- ✗ 行政書士への「再委託」
💡 「取次」と「作成」は全く別物
登録支援機関は申請書類を入管に「持っていく」こと(取次)はできます。しかし、書類を「作る」ことはできません。
この違いを理解していない受入企業が非常に多いです。「支援機関が申請してくれている」と思っていても、実際には違法な書類作成代行をさせている可能性があります。
2026年の行政書士法改正で何が変わったのか
2025年6月、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、2026年1月1日に施行されました。この行政書士法改正の本質は、「グレーゾーン」の完全消滅です。
改正ポイント①:「いかなる名目でも」違法に
🚨 改正法の核心
改正前:「報酬を得て」書類作成を行うことが禁止
改正後:「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」書類作成を行うことが禁止
この「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加されたことで、以下の行為がすべて明確に違法となりました。
- 「コンサルティング料」「サポート料」名目での書類作成代行
- 「支援費用」に申請書類作成を含めるパッケージ料金
- 「無料サービス」と称しながら、他のサービス料金に上乗せ
- 「年会費」「登録料」名目で実質的な書類作成対価を得る
改正ポイント②:罰則の明確化
📜 行政書士法改正 第21条の2
1年以下の拘禁刑
または
100万円以下の罰金
改正ポイント③:法人も処罰される「両罰規定」
⚠️ 両罰規定とは
登録支援機関の職員が行政書士法違反を犯した場合、職員個人だけでなく、法人(会社)自体も処罰されるということです。
職員個人
1年以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金
法人
最大100万円の罰金
特定技能の書類作成は「誰が」やるべき?
特定技能に関する書類は多岐にわたります。それぞれ「誰が作成すべきか」を整理します。
受入企業が自社で作成できる書類
- 自社に関する届出書類(届出名義は本人)
- 雇用契約書(契約当事者として)
- 社内の管理書類・帳簿
行政書士に依頼すべき書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格変更許可申請書
- 在留期間更新許可申請書
- 1号特定技能外国人支援計画書
- その他、入管申請に必要な各種書類の作成
登録支援機関ができること
- 支援計画の「実施」(作成ではない)
- 申請書類の「取次」(作成ではない)
- 生活支援・相談対応
- 支援計画作成の「補助」(入力作業など)
💡 「補助」と「作成」の違い
登録支援機関が支援計画作成の「補助」を行うことは認められています。しかし、これは受入企業の指示のもとで入力作業を手伝う程度であり、内容を判断して書類を完成させる「作成」とは全く異なります。
⚠️ 技人国ビザで働いている方へ
技人国ビザの更新審査が厳格化されています。飲食・宿泊・製造業で「管理職」として働いていても、現場作業が多いと更新不許可になるケースが急増中。
「支援費用に含める」は違法?よくある誤解
登録支援機関から「支援費用の中に書類作成も含まれています」と言われたことはありませんか?
🚨 これは明確に違法です
行政書士法改正により「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得ての書類作成が禁止されています。
- 「支援費用に含まれている」→ 違法
- 「書類作成は無料サービス」→ 違法(他の費用に上乗せとみなされる)
- 「コンサル料として請求」→ 違法
- 「月額サポート費用に含む」→ 違法
適法な料金体系とは
✅ 正しい料金の分け方
登録支援機関への支援委託費:〇〇円(書類作成を含まない)
行政書士への書類作成費:〇〇円(企業が直接契約・支払い)
この2つが明確に分離されていることが必須です。
見積書・契約書をチェックしてください
今すぐ、登録支援機関との契約書や見積書を確認してください。以下のような記載があれば要注意です。
- 「申請サポート料」「書類作成支援」などの項目がある
- 「支援費用(申請代行込み)」などパッケージになっている
- 行政書士費用が支援機関経由で請求されている
- 料金内訳が不明確で、何にいくら払っているかわからない
「行政書士を雇っているから大丈夫」の落とし穴
登録支援機関からよく聞く言葉があります。
「うちは行政書士を雇っているから、ビザ申請も適法にやっています」
これは大きな誤解です。登録支援機関が行政書士を雇用・委託して申請業務を行うことも、明確な違法行為です。
なぜ違法なのか?
🚨 違法となる理由
ポイントは「誰が報酬を受け取っているか」です。
- 受入企業が登録支援機関に「支援費用」を支払う
- 登録支援機関がその費用の一部で行政書士を雇う・委託する
- 行政書士が書類を作成する
👉 この場合、報酬を受け取っているのは「登録支援機関」です。登録支援機関は行政書士資格を持っていないため、行政書士法違反です。
適法な方法はただ一つ
✅ 適法な特定技能申請の流れ
- 受入企業が行政書士に直接依頼する
- 受入企業が行政書士に直接報酬を支払う
- 行政書士が書類を作成・申請する
受入企業と行政書士が直接契約することが必須です。
💡 行政書士を「紹介」するのはOK
登録支援機関が行政書士を「紹介」するだけであれば問題ありません。ただし、その後の契約・報酬の支払いは、受入企業と行政書士の間で直接行う必要があります。
受入企業が直面する3つの重大リスク
「違法なのは登録支援機関でしょ?うちは依頼しただけだから関係ない」——そう思っていませんか?残念ながら、そうではありません。
リスク①:不法就労助長罪
⚠️ 入管法違反のリスク
違法な手続きに関与した場合、入管法の「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。現行の罰則でも重い制裁が科されますが、2027年4月施行予定の改正入管法でさらに厳罰化されます。
現行法
3年以下の懲役 or 300万円以下の罰金(併科あり)
2027年4月〜(予定)
5年以下の拘禁刑 or 500万円以下の罰金(併科あり)
リスク②:今後の外国人雇用への影響
- 在留資格申請の不許可率上昇
- 審査期間の長期化
- 追加書類の要求増加
- 実態調査の対象になりやすくなる
リスク③:レピュテーション毀損
- 取引先からの信用失墜
- 金融機関からの評価低下
- 採用活動への悪影響
- 外国人材からの敬遠
💬 施行後に寄せられた相談事例
事例1|登録支援機関A社
「これまで自社で申請書類を作成していたが、法改正で違法になると聞いて外注先を探し始めた。行政書士しかま事務所に依頼し、スムーズに移行できている」
事例2|受入企業B社(製造業)
「支援機関に全部お任せしていたが、書類作成が違法だったと知って驚いた。自社支援に切り替え、書類作成は行政書士に直接依頼する体制にした」
事例3|受入企業C社(飲食業)
「支援機関から『法改正で書類作成ができなくなった』と連絡があり、紹介された行政書士に依頼することになった。結果的に費用が下がり、審査もスムーズになった」
※ いずれも当事務所への実際の相談内容をもとに、個人・法人が特定されない形で再構成しています。
【チェックリスト】今すぐ確認すべきこと
📋 受入企業向けセルフチェック
📋 登録支援機関向けセルフチェック
登録支援機関と行政書士の連携——実際の流れ
「行政書士に外注したい。でも実際にどう進むのかイメージがわかない」——そんな登録支援機関の方に向けて、当事務所での連携フローをご紹介します。
1ご紹介・お問い合わせ
登録支援機関から当事務所にご連絡。対応可能な業務範囲・料金・スケジュール感を確認し、連携の方向性をすり合わせます。
2受入企業との直接連絡
行政書士法上、受入企業から行政書士への直接契約が必要です。当事務所から受入企業に直接ご連絡し、契約・ヒアリングを行います。
3三者連携での書類準備
登録支援機関の現場知見と行政書士の法的専門性を組み合わせ、精度の高い申請を実現します。
4書類作成・申請取次
当事務所で申請書類を作成し、入管への申請取次を行います。進捗は受入企業・登録支援機関の双方に共有します。
💡 三者がそれぞれの役割を果たす——これが法改正後の正しい形です
- 登録支援機関:書類作成から解放され、本来の支援業務に集中できる
- 受入企業:適法な体制で安心して外国人を雇用できる
- 行政書士:専門知識を活かした高品質な書類を作成できる
まとめ
📝 この記事のまとめ
- 登録支援機関が特定技能の書類を作成するのは違法
- 「支援費用に含める」「無料でやっている」も違法
- 「行政書士を雇っているから大丈夫」も違法
- 2026年1月の行政書士法改正で罰則が明確化(最大100万円の罰金)
- 適法な方法は「受入企業が行政書士に直接依頼」のみ
「知らなかった」では済まされない時代です。今から適切に対応すれば、「コンプライアンスを重視する信頼できる企業」として競争優位を築くことができます。
特定技能の書類作成は
行政書士にお任せください
受入企業の方も、登録支援機関の方も。
「適法な体制に切り替えたい」——そんな疑問に、専門家がお答えします。
| 申請種類 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号) | 50,000円 |
| 在留資格変更許可申請(特定技能へ変更) | 50,000円 |
| 在留期間更新許可申請(特定技能) | 30,000円 |
| 初回相談(60分) | 無料 |
📋 この記事の情報について
本記事の内容は2026年2月時点の法令・運用情報に基づいています。具体的な事案については専門家にご相談ください。本記事の内容により生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。