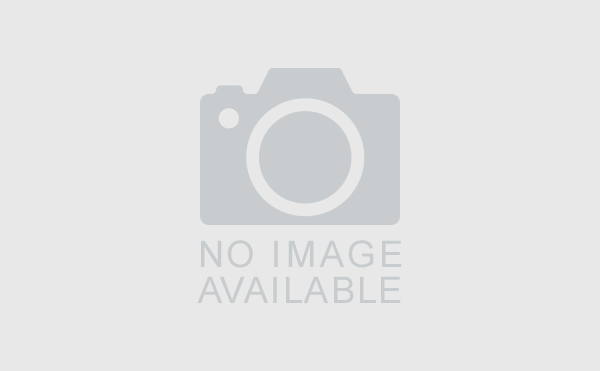「1号特定技能外国人支援計画」作成・実施の注意点|義務を怠った場合の罰則と改善命令リスク
「1号特定技能外国人支援計画」作成・実施の注意点
義務を怠った場合の罰則と改善命令リスク
この記事を読めばわかること
- 法律で定められた「1号特定技能外国人支援計画」10項目の全内容と具体的実施方法
- 「支援を怠った」と判断される具体的なケースと義務違反の実例
- 入管からの「改善命令」とは何か、その後の流れと深刻なリスク
- 支援義務違反に対する具体的な罰則(6ヶ月以下の拘禁刑・30万円以下の罰金等)
- 適法な支援体制を構築するための必須チェックポイントと記録保存義務
その支援計画、形式だけになっていませんか?
「支援計画は作ったけど、ちゃんと実施できているか自信がない…」
「定期的な面談って、具体的に何をどこまでやればいいの?」
「もし入管から『支援が不十分だ』と指摘されたら、どうなる?」
「登録支援機関に任せているから、うちは大丈夫…だよね?」
「罰則があるとは聞くけど、実際どんな時に適用されるの?」
目次
1. はじめに:特定技能制度の心臓部、「支援計画」の重要性
こんにちは、行政書士しかま事務所の鹿間です。当事務所では、特定技能制度における受入れ企業および登録支援機関のコンプライアンス体制構築を専門的にサポートしています。
特定技能制度は、単に労働力を受け入れるだけでなく、外国人が日本で安定して生活し、円滑に就労できるよう「支援」することとセットになった制度です。その支援の設計図となるのが「1号特定技能外国人支援計画」であり、この計画の適正な作成と実施こそが、制度活用の成否を分ける心臓部といえます。
しかし、多くの企業が「支援計画は作成したが、具体的にどこまで実施すべきかわからない」「形式的な支援になってしまっている」という課題を抱えています。そして、支援義務の不履行は、単なる行政指導では済まない、深刻な法的リスクを伴います。
本記事では、法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月版)を基に、支援計画の具体的な内容と、義務を怠った場合の重大なリスクについて、行政書士として徹底解説いたします。
2. 【完全解説】法律が求める「10項目の義務的支援」とその実践
運用要領別冊において明確に規定されている通り、「義務的支援はその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。また、義務的支援の全てを行わなければ、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していないこととなります」とされています。
①事前ガイダンスの提供
在留資格認定証明書交付申請前に、特定技能雇用契約の内容、上陸及び在留の条件、活動内容、留意事項等の情報提供を本人確認の上で対面またはテレビ電話等にて実施します。
実施内容の詳細
- 労働条件・活動内容の詳細説明
- 保証金等の有無の確認
- 送迎・住居・相談体制・担当者連絡先等の網羅的説明
- 外国人に十分理解させ、署名取得必須
- 確認書(参考様式第5-9号)の作成・保存
②出入国する際の送迎
入国時:上陸港・空港⇔事業所または住居間の送迎
出国時:港や空港まで送迎し、保安検査場まで同行し入場確認
重要な留意点
- 実費(交通費等)は受入れ側負担
- 保安検査場での入場確認まで責任を負う
- 送迎記録の作成・保存
③適切な住居の確保、生活に必要な契約支援
住居未確保時は、(1)情報提供し必要に応じて同行、(2)受入機関が賃借人となり貸与、(3)社宅提供のいずれかを本人希望に基づき実施します。
具体的基準
- 室内面積7.5㎡/人(技能実習からの転換時は4.5㎡/人(寝室))
- 連帯保証人、緊急連絡先等の支援
- 家賃保証料は必ず受入側負担
- 金融機関口座、携帯契約等も同様に支援
- 本人への過度負担は禁止
④生活オリエンテーションの実施
日本到着後(または在留資格変更後)、生活一般、法的届出、相談連絡先、医療、防災、防犯、法令遵守、緊急対応等について詳細な説明を行います。
実施要件
- 本人が理解する言語で8時間以上実施
- 同一機関等からの継続受入れでも4時間未満は不可
- 質問・応答可能な体制必須
- 署名取得・記録保存(参考様式第5-8号)
⑤日本語学習の機会の提供
日本語教室や教材、オンライン講座の紹介・入学手続補助等、希望に応じた支援を選択・提供します。
支援内容にかかる費用(教材、情報提供等)は受入側負担
⑥相談または苦情への対応
外国人から申出受理時、適切・迅速に対応し、必要な助言・指導を行い、必要に応じ行政機関への案内・同行を実施します。
- 外国人が理解できる言語で実施
- 週3回以上対応
- 休日・夜間にも体制構築
- 相談記録書(参考様式第5-4号)作成・保存
⑦日本人との交流促進
地方自治体等の交流行事・自治会の案内、行事参加補助、地方行事への同行支援を実施します。
年間を通じて企画案内が望ましいとされています。
⑧外国人の責に帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援
受入側都合による解除時、受入業界他企業やハローワーク紹介、必要に応じ推薦状作成・同行・諸手続情報提供を実施します。
- 次の雇用先決定まで支援継続
- 行政届出義務あり
- 転職活動のための有給休暇付与
⑨定期的な面談の実施・行政機関への通報
外国人及び監督者と3カ月に1回以上、対面または同意があればオンラインで面談し、労働・生活状況等を確認します。
- 法令違反等があれば関係機関へ通報義務
- 面談内容の記録・保存(参考様式第5-5号、第5-6号)
- オンライン時は録画保存・年1回対面実施推奨
- 録画記録は契約終了から1年以上保管
⑩支援計画に記載したその他の事項
各支援項目に日常生活・社会生活等の支援実態が直結し、原則として必須義務の網羅実施が求められます。
地方自治体の共生施策の確認・案内、市区町村との連携も含まれます。
3. これはNG!「支援義務の不履行」と見なされる具体例
運用要領別冊では、支援義務違反について明確に規定されています。以下のようなケースは、即座に「適正な実施をしていない」と判断されるリスクがあります。
【危険】義務的支援の一部未実施
- 面談を実施しているが、形式的で記録を残していない
- 本人が「不要」と言ったからという理由で、日本語学習の機会を全く提供していない
- 相談窓口を設置しているが、本人が理解できる言語に対応できる体制がない
- 生活オリエンテーションの実施時間が8時間未満(継続受入れでも4時間未満)
【厳禁】支援費用の本人負担
- 義務的支援に要する費用を直接・間接に外国人本人に負担させる
- 住居確保の支援として、不当に高額な賃料の物件を斡旋する
- 家賃債務保証料を給与から天引きする
- 送迎費用、オリエンテーション費用を本人に請求する
【重大違反】記録・書類作成義務の不履行
- 事前ガイダンス・生活オリエンテーションの確認書未作成・署名未取得
- 定期面談記録の未作成・未保存
- オンライン面談時の録画記録未保存(契約終了1年以上保管義務)
- 相談・苦情対応記録の未作成
【登録支援機関の重大違反】
- 支援の再委託(多重委託)を行う
- 委託された支援の一部を実効性なく実施
- 委託契約書に支援範囲を明記していない
- 費用の内訳開示を怠る
行政書士ワンポイント解説
運用要領では「義務的支援はその全てを行う必要があり」と明記されており、一つでも欠けると制度違反となります。特に「外国人本人が不要と言った」は免責理由になりません。また、支援計画に記載した任意的支援を行わない場合も不履行と見なされるため、計画作成時から慎重な検討が必要です。
4. 【要注意】義務を怠った企業に何が起こるか?行政処分と罰則
支援義務の不履行は、単なる行政指導では済まない深刻な結果を招きます。運用要領に基づく行政処分の流れと具体的な罰則について詳しく解説します。
行政処分の流れ
指導及び助言(入管法第19条の19)
まず入管から是正を求める指導が入ります。この段階で迅速に改善することが重要です。
改善命令(入管法第19条の21)
指導に従わない場合、期限を定めた改善命令が出されます。改善命令を受けると、その事実が公示されるため、企業の信用に深刻な影響を与えます。
欠格事由への該当・登録取消し
改善命令違反や、悪質な法令違反は、特定技能所属機関の欠格事由に該当し、今後5年間、特定技能外国人の受け入れができなくなる重大なリスクがあります。
具体的な罰則
刑事罰(入管法第71条の3)
改善命令に違反した場合:6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
改善命令は単なる行政指導ではなく、違反すれば刑事処分の対象となる重大な命令です。
届出義務違反等(入管法第71条の4、第77条の2)
各種届出義務違反:30万円以下の罰金または10万円以下の過料
- 虚偽の届出を行った場合
- 届出を怠った場合
- 報告徴収に応じない、虚偽報告をした場合
両罰規定(入管法第76条の2)
違反行為を行った従業員だけでなく、法人自体も罰金刑の対象
「担当者が勝手にやった」では済まされず、企業としての責任が問われます。
特に重要な留意点
- 改善命令の公示:改善命令を受けた事実は公示されるため、企業の信用失墜は避けられません
- 5年間の受入停止:欠格事由に該当すると、今後5年間は特定技能外国人の受入れが一切できません
- 既存外国人への影響:受入停止となった場合、現在雇用中の特定技能外国人の雇用継続も困難になる可能性があります
- 関連する在留資格への影響:入管からの処分歴は、他の在留資格申請でも不利に働く可能性があります
5. 登録支援機関への「丸投げ」は危険?委託する際の企業の責任
多くの企業が登録支援機関に支援を委託していますが、「委託したから安心」は大きな誤解です。運用要領では委託時の企業責任について明確に規定しています。
委託時の基本原則
運用要領の規定(重要)
「登録支援機関へ1号特定技能外国人支援計画の全部委託時は『適正な実施確保の基準』に適合とみなす。ただし、委託先の体制に実効性がない場合は認められない。」
つまり、形式的に委託契約を結んでも、実際に適切な支援が行われなければ基準違反となります。
受入れ機関の継続的責任
1. 支援計画の作成責任
支援計画作成自体は受入れ機関の責任です。登録支援機関は実施を担うのみで、計画の適正性は受入れ機関が保証する必要があります。
2. 委託先の監督・管理責任
委託した登録支援機関が適切に支援を実施しているかを監督・管理する責任があります。定期的な実施状況の確認と報告受領が不可欠です。
3. 費用の透明性確保
契約前に費用額・内訳の開示が必要で、複数見積もり取得が推奨されています。不透明な費用設定は問題視される可能性があります。
委託時の禁止事項
絶対に禁止される行為
- 再委託(多重委託)は不可:登録支援機関が他機関に再委託することは厳格に禁止
- 実務補助目的の外注のみ可:通訳・タクシー等の単純業務委託は可能
- 委託範囲を支援計画に明記しない:何を委託するのか不明確な契約は認められない
- 部分委託時の責任放棄:未委託部分は受入れ機関自身が基準適合責任を負う
適切な登録支援機関の選定基準
確認すべきポイント
- 実効性のある支援体制:支援責任者・担当者の適切な配置と経験
- 外国人が理解できる言語での対応体制:単なる通訳ではなく、専門的な相談対応能力
- 24時間・365日の相談体制:緊急時対応を含む包括的なサポート体制
- 過去の行政処分歴:5年以内の法令違反や行政処分の有無
- 定期報告体制:支援実施状況の詳細な報告とフィードバック体制
委託時のリスク
登録支援機関が支援義務を怠った場合、結果として受入れ企業が指導の対象となったり、外国人材の雇用継続が困難になったりするリスクがあります。
「登録支援機関に任せているから大丈夫」ではなく、「登録支援機関と共に適切な支援を実施している」という意識が重要です。
6. コンプライアンス遵守のための社内体制チェックポイント
運用要領に基づき、企業が自社の支援体制を点検できるチェックリストを提示します。定期的な自己診断により、法令違反のリスクを事前に回避しましょう。
支援体制の基本チェック
記録・書類管理チェック
費用負担・処遇チェック
委託管理チェック(登録支援機関利用時)
届出・報告義務チェック
チェック結果が不適切な場合のリスク
上記チェックポイントで「できていない」項目がある場合、支援義務違反として以下のリスクが発生します
- 出入国在留管理局からの指導・助言
- 改善命令とその公示(企業信用の失墜)
- 30万円以下の罰金または6ヶ月以下の拘禁刑
- 5年間の特定技能外国人受入れ停止
7. まとめ:適正な支援が、企業と外国人材の未来を守る
「1号特定技能外国人支援計画」の適正な実施は、単なる法的義務に留まらず、外国人社員が日本で安心して能力を発揮し、企業に定着するための基盤です。本記事では、法務省運用要領別冊に基づき、支援計画の重要なポイントを詳しく解説してまいりました。
本記事の重要ポイント
- 義務的支援10項目の全て実施:一つでも欠けると制度違反となり、改善命令・罰則の対象
- 支援費用の直接・間接負担禁止:外国人本人に負担させることは厳格に禁止
- 詳細な記録作成・保存義務:各支援の確認書作成、署名取得、適切な保管が必須
- 改善命令違反の重大リスク:6ヶ月以下の拘禁刑・30万円以下の罰金、5年間の受入停止
- 登録支援機関委託時の企業責任:委託しても企業の監督・管理責任は継続
義務の不履行は、罰則や改善命令といった直接的なペナルティだけでなく、企業の評判や今後の採用活動にも深刻な影響を及ぼします。また、改善命令を受けた事実は公示されるため、取引先や求職者からの信頼失墜は避けられません。
適正な支援がもたらす価値
企業にとって
- 優秀な外国人材の定着・活躍
- 法令遵守による信頼性向上
- 安定した人材確保体制の構築
- 行政処分リスクの回避
外国人材にとって
- 安心・安全な日本生活の実現
- 適切な労働環境での能力発揮
- 日本社会への円滑な統合
- キャリア形成機会の拡大
特定技能制度は、企業の人手不足対策として有効ですが、受入れ企業には多くの法的義務と責任が伴います。特に2025年4月からの届出頻度変更や、地域共生施策との連携など、最新の運用ルールを正確に把握し、遵守することが重要です。
法令遵守の体制を整えることが、結果的に企業と外国人材双方にとっての最大の利益となります。計画的かつ誠実な支援の実施が、持続可能な外国人材活用と企業の発展につながるのです。
最後に重要な注意
特定技能制度の運用は常にアップデートされており、「知らなかった」では済まされない事態になる可能性があります。制度の活用に際しては、最新の情報を収集しつつ、必要に応じて専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
行政書士しかま事務所の「特定技能コンプライアンス」サポート
特定技能制度のコンプライアンス、専門家が貴社のリスク管理を徹底サポートします
コンプライアンス診断・監査
- 現行の支援・届出体制の法的適合性診断
- 義務的支援10項目の実施状況詳細チェック
- 記録・書類管理体制の適正性確認
- 改善すべき点の具体的提案
支援計画・契約書作成支援
- 法令要件を満たした支援計画の作成・レビュー
- 登録支援機関との委託契約書チェック
- 特定技能雇用契約書の適正性確認
- 各種確認書・報告書様式の整備
社内研修・マニュアル作成
- 支援担当者向け実務研修の実施
- 社内コンプライアンスマニュアル作成
- 最新の法改正情報の定期提供
- 緊急時対応フローの策定
行政対応・危機管理サポート
- 入管からの指導・改善命令への対応支援
- 各種届出手続きの代行・チェック
- 特異事案発生時の緊急対応
- 行政処分リスクの事前回避策提案
「知らなかった」では済まされない事態になる前に、ぜひご相談ください
情報の時点:本記事は法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月版)および2025年6月22日時点の法令情報に基づいて作成しています。
免責事項:法改正や運用変更により内容が変更される可能性があります。個別具体的な事案については、必ず最新情報を確認の上、専門家にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。03-6824-7297営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております