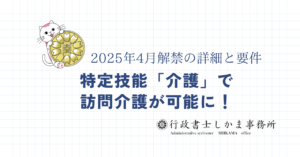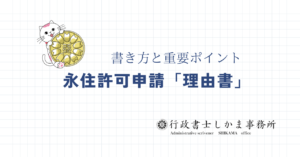【特定技能】建設分野の受入要件・手続きを完全解説
【特定技能】建設分野の受入要件・
手続きを完全解説
建設分野の特定技能は、他分野より手続きが複雑。建設業許可、JAC加入、CCUS登録、建設特定技能受入計画の認定など、建設分野特有の要件から、土木・建築・ライフライン設備の業務区分、1号・2号の違いまで行政書士が完全解説します。
⚠️ 建設分野は他分野より要件が厳格
建設業許可 + JAC加入 + CCUS登録 +
建設特定技能受入計画の認定が必要
認定申請から認定まで1.5〜4か月かかるため、早めの準備が必須
建設業許可
建設業法第3条の許可が必須
JAC加入
特定技能外国人受入事業実施法人への加入
CCUS登録
建設キャリアアップシステムへの登録
📞 「建設特定技能の手続き、何から始めればいい?」
JAC加入からCCUS登録、受入計画認定、在留資格申請まで一括サポートします。
特定技能「建設」とは
平成30年12月、出入国管理及び難民認定法の一部改正により、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。この制度は、深刻な人手不足が認められた16分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材の就労を可能にするものです。
📋 建設業界の人手不足の現状
建設業界では特に深刻な人手不足に直面しています。就業者数は1997年の685万人をピークに2020年時点では505万人まで減少。生産性向上や国内人材の確保の取組だけでは対応できず、即戦力となる外国人材を受け入れる制度として特定技能「建設」が注目されています。
特定技能「建設」の特徴
・技能実習2号修了者が引き続き最長5年間就労可能
・帰国した技能実習修了者を再度雇用することも可能
・特定技能2号への移行により長期的な雇用も視野に
・技能実習とは異なり、実習ではなく労働者として受入可能
業務区分(土木・建築・ライフライン設備)
建設分野の特定技能は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務区分に分かれています。
特定技能1号の業務区分
| 区分 | 業務内容 |
|---|---|
| 土木 | 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事 |
| 建築 | 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事 |
| ライフライン・設備 | 指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事 |
特定技能2号の業務区分
| 区分 | 業務内容 |
|---|---|
| 土木 | 複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理 |
| 建築 | 複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理 |
| ライフライン・設備 | 複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理 |
✅ 業務区分のポイント
在留資格上の業務区分は、作業の性質による分類であり、作業現場の種類による分類ではありません。認定を受けた在留資格に含まれる工事業であれば、現場の種類を問わず従事することができます。
人材要件(1号・2号の違い)
特定技能1号の要件
| 技能水準 | 以下のいずれかに該当すること ・「建設分野特定技能1号評価試験」に合格 ・「技能検定3級」に合格 ・建設分野の技能実習2号を良好に修了(試験免除) |
| 日本語能力 | 以下のいずれかに該当すること ・「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格 ・「日本語能力試験(N4以上)」に合格 ・技能実習2号を良好に修了(試験免除) |
特定技能2号の要件
| 技能水準 | 以下のいずれかに該当すること ・「建設分野特定技能2号評価試験」に合格 ・「技能検定1級」に合格 ・「技能検定単一等級」に合格 |
| 実務経験 | 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長・職長)としての実務経験が必要 |
📋 1号と2号の違い
・1号:在留期間は通算5年まで、家族帯同不可
・2号:在留期間の更新上限なし、家族帯同可能
2号は「複数の技能者を指導し、工程を管理する」レベルの技能と経験が必要です。
受入企業の要件(建設分野特有)
建設分野では他の特定技能分野と比較して、より厳格な受入要件が設けられています。
🚨 建設分野特有の要件が多数
建設現場の特殊性に配慮し、適正な就労環境確保のため、他分野にはない要件が多数あります。特に「建設特定技能受入計画」の認定が必須であり、認定までに1.5〜4か月かかるため、早めの準備が必要です。
受入企業が満たすべき要件
- 建設業法第3条の許可を取得していること
- 国内人材確保の取組を行っていること
- 外国人に対し、同等の技能を持つ日本人と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
- 雇用契約締結前に、重要事項を外国人が理解できる言語で説明すること
- 企業と特定技能外国人を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録すること
- 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC等)に加入すること
- 特定技能1号外国人の人数が企業の常勤職員総数を超えないこと
- 報酬予定額、安全・技能習得計画等を記載した「建設特定技能受入計画」の認定を国土交通省から受けること
- 国土交通省または委託機関による計画履行状況の確認を受けること
- 国土交通省の調査や指導に協力すること
- 特定技能外国人の求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
⚠️ JAC(建設技能人材機構)への加入が必須
建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC等)への加入が必要です。JACは国土交通大臣が登録した法人で、受入企業の巡回指導や外国人への相談対応などを行います。
受入れまでの手続きの流れ
建設分野の特定技能受入れは、他分野より手続きが多いため、計画的な準備が必要です。
受入れまでの流れ
建設業法第3条許可の取得
地方整備局等または各都道府県で取得。建設特定技能受入計画の認定申請に必要。
建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
一般財団法人建設業振興基金にて登録。企業と特定技能外国人の両方の登録が必要。
特定技能外国人受入事業実施法人(JAC等)への加入
建設分野特有の要件。加入手続きを行う。
特定技能雇用契約に係る重要事項説明
外国人が理解できる言語で説明。
特定技能雇用契約の締結
報酬額、労働条件等を明記した契約を締結。
1号特定技能外国人支援計画の作成
10項目の支援内容を含む計画を作成。
建設特定技能受入計画の作成・認定申請(オンライン)
国土交通省に申請。審査完了まで通常1.5〜2か月(地域によっては3〜4か月)。技能実習からの移行は修了日の6か月前から申請可能。
在留資格認定証明書交付申請 or 在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁に申請。建設特定技能受入計画の認定がないと許可されない。
受入れ後の手続き
1号特定技能外国人受入報告書の提出
受入後1か月以内にオンライン申請。
特定技能外国人の監理業務を行う担当者講習会受講
受入れ後、概ね6か月以内に受講。
🚨 申請時の注意点
・建設特定技能受入計画認定申請と出入国在留管理庁への申請は並行して行えるが、受入計画の認定がないと在留資格は許可されない
・就労管理システムで「引き戻し・再編集」をすると、再申請日の順で審査が開始される
・認定までは地域によっては数か月かかるため、早めの申請が必須
特定技能「建設」のメリット
🏢 雇用側のメリット
- 即戦力となる外国人材の確保が可能
- 技能実習修了者の継続雇用による教育コスト削減
- 特定技能2号への移行による長期的な人材確保
- 技能実習とは異なり、労働者として受入可能
- 職種や作業の制限が技能実習より緩和
👷 外国人材のメリット
- 技能実習修了後も最大5年間、日本で就労可能
- 技能向上による特定技能2号への移行機会
- 特定技能2号取得後は在留期間の更新上限なし
- 特定技能2号では家族の帯同が可能
- 日本の建設技術習得による自国でのキャリア向上
料金・サポート内容
当事務所では、建設分野の特定技能受入れをトータルサポートしています。JAC加入からCCUS登録、建設特定技能受入計画の認定、在留資格申請まで一括対応します。
💰 特定技能「建設」申請の料金
在留資格申請 + 建設特定技能受入計画認定申請
+ 建設分野特有の手続き
建設特定技能受入計画 認定申請:80,000円(税抜)
✅ 当事務所のサポート内容
・申請手続きの代行:建設特定技能受入計画作成・申請、各種届出、在留資格申請
・制度導入のコンサルティング:特定技能制度の詳細説明、企業様の状況に合わせた導入計画
・関連機関への加入手続き支援:JAC加入、CCUS登録のサポート
・受入後の各種サポート:定期報告書類の作成・提出、在留期間更新手続き、計画変更申請
・特定技能2号への移行支援:1号から2号への移行手続きをサポート
当事務所の特徴
・信頼・誠実な対応:お客様との信頼関係を第一に、誠実で透明なコミュニケーションを重視
・専門知識と柔軟な対応力:特定技能制度に特化した専門知識と柔軟な対応力で、複雑な手続きもスムーズに対応
・個別対応と継続的なサポート:企業様ごとの状況に合わせた個別対応を徹底し、受入れから在留中のサポートまで幅広く対応
まとめ:建設分野は早めの準備が必須
📝 この記事のまとめ
- 建設分野は他分野より要件が厳格:建設業許可、JAC加入、CCUS登録、受入計画認定が必要
- 業務区分は3つ:土木、建築、ライフライン・設備
- 1号と2号の違い:2号は在留期間の更新上限なし、家族帯同可能
- 建設特定技能受入計画の認定が必須:認定まで1.5〜4か月かかる
- 技能実習修了者は試験免除:特定技能1号への移行がスムーズ
⚠️ 早めの準備が重要
建設分野の特定技能は手続きが複雑で、認定までに時間がかかります。技能実習修了の6か月前から準備を始めることをお勧めします。
特定技能「建設」の受入れは
当事務所にお任せください
JAC加入からCCUS登録、建設特定技能受入計画の認定、在留資格申請まで
建設分野特有の複雑な手続きを一括サポートします。
平日9:00〜18:00 / 全国オンライン対応
🚨 「技能実習生を特定技能に移行させたい」
技能実習2号修了者は試験免除で移行可能。修了6か月前から準備を始めましょう。
📋 この記事の情報について
本記事の内容は2025年12月16日時点の情報に基づいて作成しており、一般的な情報提供を目的としています。法令改正や運用変更により内容が変わる場合がありますので、最新情報は国土交通省・出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。個別のケースによって判断が異なる場合がありますので、具体的な申請に関しては専門家にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。03-6824-7297営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております