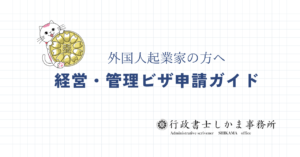技能実習制度の廃止と新在留資格「育成就労」について
技能実習制度の廃止と新在留資格「育成就労」について
はじめに
2024年6月14日、技能実習に代わる新たな制度「育成就労」を新設するための関連法の改正が国会で可決・成立しました。 長年にわたり様々な問題点が指摘されてきた技能実習制度は2030年までに廃止され、新たに「育成就労」という在留資格が創設されることになりました。 本記事では、技能実習制度が廃止される背景と、新制度「育成就労」の概要や特徴について解説します。
技能実習制度が廃止される背景
1993年から続いてきた技能実習制度は、外国人が日本で技能を身につけて母国の発展に貢献するという「国際貢献」を掲げた制度でした。 しかし、実際には深刻な人手不足に対応するための「労働力確保」という側面が強まり、制度の目的と実態の乖離が問題視されてきました。
技能実習制度の主な問題点
- 低賃金・残業代未払いなどの労働条件の問題
- 長時間労働や不当な労働環境による人権侵害
- 転職・転籍の自由がなく、問題があっても職場を変えられない
- 不適切な待遇や労働環境による失踪者の増加
- 制度目的(国際貢献)と実態(労働力確保)の乖離
こうした問題を解決するため、政府は技能実習制度を抜本的に見直し、人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」を新たに創設することとしました。
新制度「育成就労」の概要
育成就労制度は、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度です。 制度の目的を「国際貢献」から「日本の産業発展」へと転換し、外国人材がキャリアアップできる環境を整備することで、外国人から「選ばれる国」を目指しています。
育成就労制度の主な特徴
- 日本の人手不足分野における人材育成と人材確保が目的
- 基本的な在留期間は原則3年間
- 特定技能への移行を前提とした制度設計
- 一定の条件の下で転籍(職場変更)が可能
- 就労開始前に日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5等)が必要
- 外国人の権利保護の仕組みが強化
育成就労制度では、技能実習制度での「技能実習生」に相当する外国人を「育成就労外国人」と呼びます。 また、技能実習制度における「監理団体」に相当する組織は「監理支援機関」となり、監理・支援・保護機能が強化されます。
技能実習制度と育成就労制度の主な違い
以下の表で、技能実習制度と新たな育成就労制度の主な違いを比較します。
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能等の修得を通じた国際貢献 | 日本の人手不足分野における人材育成と人材確保 |
| 在留期間 | 最長5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年) | 原則3年(特定技能への移行が前提) |
| 受入れ時の条件 | 特になし(各職種で必要な要件あり) | 日本語能力A1相当以上(N5等)が必要 |
| 転職・転籍 | 原則不可(人権侵害等があった場合のみ) | 一定条件下で可能(同一業務区分で一定期間就労後等) |
| 特定技能への移行 | 2号良好修了後、試験免除で特定技能1号へ移行可 | 技能試験・日本語試験の合格が必要 |
| 家族の帯同 | 不可 | 原則不可 |
| 受入れ形態 | 企業単独型と団体監理型の2種類 | 単独型育成就労と監理型育成就労の2種類 |
育成就労制度では、技能実習制度とは異なり、外国人本人の意向による転籍が一定条件下で認められます。ただし、転籍には以下の条件が必要です。
- 転籍先の業務が転籍元と同一の業務区分であること
- 転籍元での就労期間が育成就労産業分野ごとに定められた期間(1年以上2年以下の範囲)を超えていること
- 育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
- 転籍先の育成就労実施者が適切と認められる要件に適合していること
また、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合は、上記条件に関わらず転籍が認められます。
施行スケジュール
育成就労制度に関する法改正は2024年6月21日に公布され、公布日から起算して3年以内に施行されることが決まっています。 最新の報道によると、政府は2027年4月1日の施行で調整を進めているとされています。
主なスケジュール
- 2024年6月21日:関連法の公布
- 2027年4月1日:育成就労制度施行(予定)
- 施行日〜3年間:移行期間(激変緩和措置)
- 2030年頃:技能実習制度の完全廃止
技能実習生の受入れは、改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3ヶ月を経過するまでに技能実習を開始するものまでとなります。 また、施行日時点で既に在留している技能実習生については、認定された技能実習計画に基づいて引き続き技能実習を行うことができます。
事業者がすべき準備
現在技能実習生を受け入れている、または今後外国人材の受け入れを検討している事業者は、以下のような準備を進めることをおすすめします。
- 最新情報の確認
出入国在留管理庁や厚生労働省のウェブサイト等で育成就労制度に関する最新情報を定期的に確認しましょう。 - 受入れ計画の見直し
育成就労制度では原則3年間の就労を通じた人材育成が目的となるため、現在の受入れ計画を見直す必要があります。 - 監理支援機関の選定
現在取引のある監理団体が新制度でも監理支援機関となる予定かどうか確認し、必要に応じて新たな監理支援機関を検討しましょう。 - 日本語教育の体制整備
育成就労制度では日本語能力の要件が追加されるため、外国人材への日本語教育支援体制を整備しましょう。 - 特定技能への移行支援体制の構築
育成就労から特定技能への移行には試験合格が必要となるため、技能試験・日本語試験対策の支援体制を構築しましょう。
注意点
育成就労制度の受入れ対象分野(育成就労産業分野)は、施行日までの間に有識者や労使団体等で構成する会議体の意見を聴いて決定されます。 現在技能実習制度で認められている全ての職種・作業が育成就労制度に移行するわけではないため、自社の業種が対象となるか確認が必要です。
まとめ
技能実習制度に代わる新たな「育成就労制度」は、外国人材の権利保護を強化し、キャリアアップの道筋を明確にした制度として期待されています。 制度の目的が「国際貢献」から「日本の人手不足分野における人材育成と人材確保」へと変わることで、より実態に即した制度設計となりました。
新制度への移行には、まだ2年程度の時間がありますが、スムーズな移行のためには早めの準備と情報収集が欠かせません。 当事務所では、技能実習制度から育成就労制度への移行に関するご相談や手続きのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。