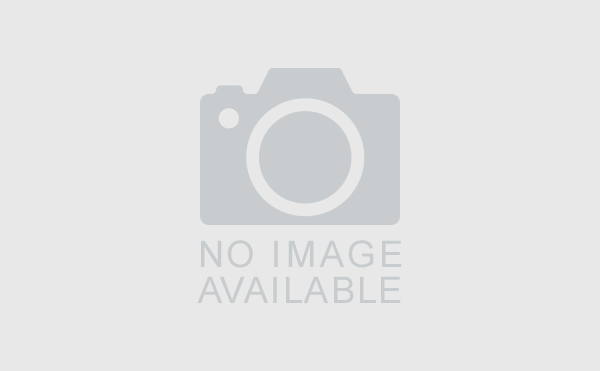特定技能運用要領解説①
【2025年最新/特定技能入門編】
初めての外国人採用、制度の基本から受入れの流れまで完全ガイド
この記事を読むとわかること
- 特定技能制度の創設目的と基本的な仕組み
- 特定技能1号と2号の違いと対象16分野
- 海外・国内からの受入れ手続きの具体的な流れ
- 受入れ企業が満たすべき基本的な基準と責務
- 雇用契約で注意すべき重要なポイント
特定技能、何から始めれば?
「人手不足が深刻で外国人採用を検討しているが、特定技能制度がよく分からない」 「制度は知っているが、実際の手続きや企業の責任について詳しく知りたい」 「何から始めればいいのか、全体像を把握したい」
このような疑問をお持ちの企業経営者や人事担当者の方に向けて、行政書士の専門的な視点から、 出入国在留管理庁の最新運用要領(令和7年6月版)に基づき、特定技能制度の基本から実際の受入れの流れまでを 分かりやすく解説いたします。
目次
第1章 特定技能制度とは?創設の目的と基本構造
1-1. 制度創設の目的
深刻な人手不足への対応
出入国在留管理庁の運用要領によると、特定技能制度は「中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、 我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきている」状況を受けて創設されました。
この制度の目的は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある 産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することです。
1-2. 特定技能1号と2号の主な違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 (特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準) | 熟練した技能 (現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能) |
| 在留期間 | 1年、6月又は4月ごと (通算で上限5年) | 3年、1年又は6月ごと (更新回数に制限なし) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同可能 |
| 支援計画 | 1号特定技能外国人支援計画の策定・実施が必要 | 支援計画の策定・実施は不要 |
| 対象分野 | 16分野すべて | 11分野のみ |
1-3. 対象となる16の特定産業分野
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令により、 以下の16分野が定められています。
特定技能2号は11分野に限定されており、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の5分野は1号のみとなっています。
第2章 特定技能外国人を受け入れるための主な流れ
2-1. 2つの受入れルート
特定技能外国人の受入れには、大きく分けて2つのルートがあります。 それぞれの手続きの流れと特徴を理解することが重要です。
2-2. 海外からの受入れ(新規入国)
海外ルート:手続きの流れ
各分野の技能試験及び日本語能力試験に合格
受入れ機関との間で雇用契約を締結
職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援計画を策定
地方出入国在留管理局に申請
在外日本領事館で査証申請
日本入国後、就労開始及び支援計画の実施
2-3. 国内での在留資格変更
国内ルート:手続きの流れ
国内で各試験に合格(留学生等)
受入れ機関との間で雇用契約を締結
職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援計画を策定
地方出入国在留管理局に申請
許可後、就労開始及び支援計画の実施
2-4. 手続きの重要なポイント
試験合格と雇用契約の順序
基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後、特定技能所属機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されますが、 特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできます。ただし、各試験に合格しなければ、受入れが認められません。
申請受付場所
特定技能外国人の受入れの申請は、全国の地方出入国在留管理局(空港支局を除く)で受け付けています。 また、登録支援機関の登録申請についても同様です。
第3章 受入れ企業(特定技能所属機関)の基本的な責務と基準
3-1. 企業が負うべき責務の全体像
特定技能所属機関(受入れ企業)は、以下の3つの大きな責務を負います。
1. 関係法令の遵守
出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を遵守し、 制度の意義に沿って適正に運用することを確保する責務
2. 適切な支援の実施
1号特定技能外国人が安定的かつ円滑に活動できるよう、 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する義務
3. 各種届出の履行
特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、 地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行う義務
3-2. 雇用契約で満たすべき基準
特定技能雇用契約については、以下の基準に適合していることが必要です。
業務内容に関する基準
- 業務内容が分野省令で定める特定産業分野に該当すること
- 関連業務を含めても、業務時間の半分以上が主たる業務であること
報酬に関する基準
重要:日本人と同等以上の報酬
特定技能外国人の報酬額が、日本人が従事する場合に受ける報酬の額と同等以上であることが必要です。
- 報酬は通貨で支払われること
- 報酬の額は、労働時間に応じて適切に決定されること
- 報酬は、月1回以上定期的に支払われること
差別禁止・権利保護に関する基準
- 外国人であることを理由とした差別的取扱いをしないこと
- 一時帰国を希望した場合、必要な有給休暇を取得させること
- 帰国旅費を担保する措置を講じること
3-3. 企業自体が満たすべき基準
特定技能所属機関自身についても、以下の基準に適合していることが求められます。
法令遵守に関する基準
- 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
- 過去1年間に、非自発的離職者を発生させていないこと
- 過去1年間に、行方不明者を発生させていないこと
欠格事由に関する基準
5年以内の法令違反がないこと
特定技能所属機関又はその役員が、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと
- 暴力団関係者等でないこと
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等でないこと
事業の継続性に関する基準
継続履行体制の確保
特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること、 すなわち、事業を安定的に継続しうる財政的基盤があることが必要です。
- 適切な事業計画を有していること
- 雇用契約を継続して履行するに足りる財政的基盤を有していること
3-4. 1号特定技能外国人支援計画の重要性
支援計画は企業の最重要義務
1号特定技能外国人支援計画の策定・実施は、企業の最も重要な義務の一つです。 この支援計画には、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援が含まれ、 外国人が安定的かつ円滑に活動できるようにするための具体的な取組みを定める必要があります。
企業は、他の者に支援計画の全部又は一部の実施を委託することができ、 登録支援機関に全部の実施を委託した場合は、一定の基準に適合しているとみなされます。
まとめと次回予告
今回のまとめ
本記事では、特定技能制度の基本的な仕組みから、受入れ手続きの流れ、企業が満たすべき基本的な基準まで、 出入国在留管理庁の最新運用要領に基づいて解説いたしました。
制度の基本理解
人手不足解消を目的とした制度で、1号・2号の違いや16の対象分野について理解
受入れの流れ
海外からの新規入国と国内での在留資格変更の2つのルートとその手続き
企業の基本要件
法令遵守、適正な雇用契約、支援計画の実施という3つの大きな責務
次回予告:【実践編】支援計画と登録支援機関の活用法
次回の連載第2回では、企業の最重要義務である「1号特定技能外国人支援計画」について、 具体的な内容と実施方法を詳しく解説いたします。
- 支援計画に含めるべき10の支援項目の詳細
- 登録支援機関の選び方と委託のメリット・デメリット
- 自社で支援を実施する場合の注意点と実務上のポイント
- 支援の記録保存と行政機関への報告義務
行政書士しかま事務所
特定技能・外国人雇用の専門サポート
当事務所の特徴
- 特定技能制度に特化した専門事務所
- 最新法令・運用要領に完全対応
- 申請から受入れ後まで一貫サポート
- 登録支援機関との連携体制完備
主要サービス
- ・特定技能外国人の受入れ申請代行
- ・1号特定技能外国人支援計画の作成
- ・登録支援機関の選定サポート
- ・受入れ後の届出代行・コンプライアンス支援
特定技能外国人の受入れでお困りの企業様、まずはお気軽にご相談ください。
免責事項・情報の時点
情報の時点:本記事は、令和7年6月版「特定技能外国人受入れに関する運用要領」 (出入国在留管理庁)に基づいて作成されており、2025年6月時点の最新情報です。
免責事項:本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としており、 個別具体的な案件については、必ず最新の法令や運用要領を確認し、 専門家にご相談ください。法令等の改正により内容が変更される場合があります。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」 (令和7年6月版)
お気軽にお問い合わせください。03-6824-7297営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております