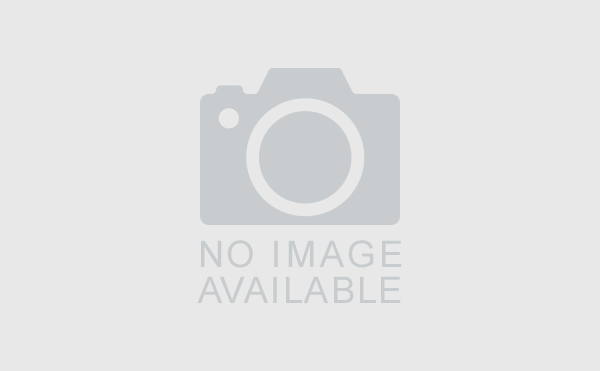「技術・人文知識・国際業務」ビザでフルリモート/在宅勤務はどこまで認められる?最新の入管運用と企業側の注意点
「技術・人文知識・国際業務」ビザでフルリモート/在宅勤務はどこまで認められる?最新の入管運用と企業側の注意点
この記事を読むとわかること
- 技人国ビザでフルリモート/在宅勤務が「原則可能」とされる背景
- 入管がリモートワークで特に注視するポイント(業務実態、指揮命令など)
- 企業が外国人リモートワーカーに対して負う労務管理・入管上の責任
- リモートワーク導入時に必要な契約書・社内規程の整備ポイント
- トラブルを避けるための具体的な対策と専門家への相談の重要性
こんなお悩みありませんか?
- 「外国人社員にフルリモートを認めても、ビザ更新で不利にならない?」
- 「在宅勤務だと、ちゃんと仕事してるか入管にどう説明すればいいの?」
- 「海外からのリモートワークは技人国ビザでOK?」
- 「リモートワーク中の労働時間管理や情報セキュリティ、どうすれば?」
- 「契約書や就業規則、外国人リモートワーカー向けに変更は必要?」
1. はじめに:外国人社員のリモートワーク、ビザの壁はある?
はじめまして、行政書士しかま事務所の代表を務めております鹿間英樹です。当事務所(https://gyousei-shikama-office.com/)では、外国人の在留資格取得・変更手続きを専門として、多くの企業様の外国人雇用をサポートしてまいりました。
新型コロナウイルス感染症の拡大以降、働き方の選択肢としてリモートワークや在宅勤務が一般化し、多くの企業において外国人社員にも同様の働き方を適用したいというご相談が増加しています。特に、グローバル化が進む現代において、優秀な外国人人材を確保・定着させるため、柔軟な働き方の提供は企業の重要な戦略の一つとなっています。
しかし、外国人社員の場合は在留資格との関連で、「どこまで許容されるのか」「企業として何を注意すべきか」「入管手続きに影響はないのか」といった疑問が生じることも事実です。特に「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国ビザ」)を持つ外国人社員については、業務の専門性や雇用管理の実態が重視されるため、リモートワーク導入時には慎重な検討が必要です。
本記事では、技人国ビザを持つ外国人社員のリモートワークについて、最新の入管運用と企業が留意すべき点を専門家の視点から詳しく解説いたします。適切な理解と対策により、外国人社員の多様な働き方を実現しながら、コンプライアンスを確保していきましょう。
2. 技人国ビザとリモートワーク:入管の基本的な考え方
原則として「可能」であること
技人国ビザの活動は、必ずしも物理的なオフィスへの出社を前提としていません。業務内容が許可範囲内であり、雇用契約が適切に維持されていれば、リモートワーク自体が直ちに問題となるわけではありません。
入国管理局(入管)は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、従事する業務の内容と雇用関係の実態を重視しています。出入国管理及び難民認定法では、技人国ビザの対象となる活動を「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」と定めています。
この定義において重要なのは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」という部分と、「専門的な技術・知識を要する業務」という部分です。つまり、適切な雇用契約の下で専門的業務に従事していれば、その業務を行う「場所」について法令上の制限はないと解釈されます。
2020年以降の新型コロナウイルス感染症拡大期においても、入管は働き方の多様化に一定の理解を示しており、感染拡大防止のためのテレワーク導入については柔軟な対応がなされました。ただし、これはあくまで「業務の実態が適切に維持される」ことが前提であることに注意が必要です。
重要なのは「活動の実態」
入管は、リモートワークという形態そのものよりも、その下で「本当に技人国ビザに該当する専門的業務を行っているか」「適正な雇用管理がなされているか」を重視します。
企業においては、リモートワークを導入する際も、外国人社員が従事する業務の専門性、雇用関係の継続性、労務管理の適切性を明確に説明できる体制を整備することが求められます。
3. 【ポイント1】業務内容の実態:本当に「技人国」の仕事?
リモートワークにおいて最も重要なポイントの一つが、外国人社員が従事する業務が確実に「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることの立証です。物理的な監督が困難になるリモートワーク環境では、業務内容の把握と記録がより一層重要になります。
技人国ビザの対象業務の確認
技人国ビザの対象となる業務は、以下のような専門的な内容に限定されています
- 技術分野:システム開発、データ分析、研究開発、設計業務など
- 人文知識分野:通訳・翻訳、貿易業務、企画・調査、法務・財務など
- 国際業務分野:海外取引、外国語教育、国際広報、海外展開支援など
企業は、リモートワークを行う外国人社員が、これらの専門的業務に確実に従事していることを証明できるよう、以下の対策を講じる必要があります
- 具体的な業務内容の文書化:日々の業務内容、使用するツール、成果物を詳細に記録
- プロジェクト管理の徹底:担当プロジェクト、役割、進捗状況の明確化
- 成果物の保管:作成した資料、レポート、プログラムコードなどの体系的保管
- 専門性の継続的向上:研修受講、資格取得などの記録維持
注意:単純労働への従事リスク
リモートワークを隠れ蓑にした単純労働への従事や、実質的な活動内容の欠如は、在留資格取消しや更新不許可の重大なリスクとなります。特に、データ入力のみ、単純な翻訳作業のみといった業務では、技人国ビザの要件を満たさない可能性があります。
企業は、外国人社員の業務が常に専門性を保持し、単純労働に陥らないよう継続的な管理と支援を行う責任があります。
4. 【ポイント2】指揮命令関係と労務管理の明確性
技人国ビザの要件として「本邦の公私の機関との契約に基づく活動」があることから、企業と外国人社員との間に明確な指揮命令関係が存在し、適切な労務管理が行われていることの証明が不可欠です。リモートワーク環境では、この関係性をより明確に示す必要があります。
指揮命令関係の明確化
企業が証明すべき要素
- 上司・部下関係の明確性:組織図、報告ラインの文書化
- 業務指示の方法:どのように指示を出し、進捗を確認するか
- 定期的なコミュニケーション:会議、面談の頻度と記録
- 評価制度:人事評価、目標設定、フィードバックの仕組み
労働時間管理の重要性
リモートワークにおける労働時間管理は、労働基準法の観点からも、在留資格の観点からも重要な要素です。「本当に働いているのか」「適正な労働時間で専門業務に従事しているのか」を客観的に証明できる体制が必要です。
推奨される労働時間管理手法
- 勤怠管理システムの活用:クラウド型勤怠管理ツールでのリアルタイム記録
- 定期的なオンライン会議:朝礼、夕礼での出退勤確認
- 日報・週報の提出:業務内容と時間の詳細な記録
- 緊急時の連絡体制:業務時間中の連絡可能性の確保
コミュニケーション体制の構築
リモートワーク環境では、対面でのコミュニケーションが困難になるため、代替手段の確立が重要です
- チャットツールの活用:Slack、Microsoft Teams等での常時コミュニケーション
- プロジェクト管理ツール:Asana、Trello、Jira等での進捗共有
- ビデオ会議:定期的な1on1ミーティング、チーム会議の実施
- 文書共有:Google Workspace、Office 365等での共同作業
これらのツールの使用履歴も、業務実態を証明する重要な資料となります。
5. 【ポイント3】日本国内での居住と活動拠点
技人国ビザは、日本国内の企業等との契約に基づき、日本国内で活動することが前提となっています。フルリモートワークの場合でも、外国人社員の日本国内での居住と活動拠点の明確性は重要な要件です。
居住地の把握と管理
企業が確認すべき事項
- 日本国内の住所:住民票、賃貸契約書等での居住実態の確認
- 在留カード情報:住所変更の適切な届出がなされているか
- 社会保険加入:健康保険、厚生年金の継続的な加入状況
- 税務上の取扱い:住民税、所得税の日本での納税実績
活動拠点としての自宅環境
リモートワークを行う自宅が、適切な「活動拠点」として機能していることも重要な確認事項です
確認が推奨される環境要素
- インターネット環境:安定した高速回線の確保
- 業務用機器:パソコン、モニター等の適切な設備
- セキュリティ対策:VPN接続、セキュリティソフトの導入
- 作業環境:集中して業務を行える空間の確保
連絡体制の確保
企業は、外国人社員との確実な連絡体制を維持する責任があります。特に緊急時や入管からの照会があった場合に、速やかに連絡が取れる体制の構築が必要です
- 複数の連絡手段:電話、メール、チャットツール等の確保
- 緊急連絡先:本人以外の家族、友人等の連絡先の把握
- 定期的な安否確認:体調管理や生活状況の把握
- 住所変更の即座報告:引越し等の際の迅速な情報更新
注意:長期の日本離脱
技人国ビザは日本での活動を前提としているため、リモートワークを理由とした長期の日本離脱(1年超など)は、在留資格の趣旨に反する可能性があります。一時的な帰国や出張は問題ありませんが、生活の拠点が海外に移ったと判断される状況は避ける必要があります。
企業は、外国人社員が継続的に日本を生活・活動の拠点としていることを客観的に証明できる体制を整備することが重要です。
6. 企業が取るべき具体的な対策と準備(契約・規程・届出)
外国人社員にリモートワークを導入する際、企業は法的リスクを回避し、適切な労務管理を行うため、以下の具体的な対策を講じる必要があります。
雇用契約書・就業規則の見直し
契約書に明記すべき事項
- 勤務場所の特例:「在宅勤務を含む」旨の明記
- 勤務時間の管理:コアタイム、連絡可能時間の設定
- 費用負担:通信費、光熱費の負担割合
- 設備・備品:貸与機器の管理責任
- 業務報告:日報・週報の提出義務
多言語対応の重要性
外国人社員が契約内容を正確に理解できるよう、以下の配慮が必要です
- 母国語での説明資料:主要な契約条項の翻訳版作成
- 理解度の確認:説明後の質疑応答、理解確認書の取得
- 継続的なフォロー:運用開始後の疑問点への対応
業務内容の明確化と記録システム
推奨される記録管理システム
- 業務管理システム:プロジェクト、タスク、進捗の一元管理
- 成果物管理:作成した資料、レポートの体系的保管
- 勤務実績記録:労働時間、業務内容の詳細な記録
- コミュニケーション履歴:会議、指示、報告の記録
情報セキュリティ対策の徹底
リモートワーク環境では、情報セキュリティリスクが高まるため、以下の対策が不可欠です
必須のセキュリティ対策
- VPN接続:社内システムへの安全なアクセス
- 多要素認証:ログイン時のセキュリティ強化
- 端末管理:貸与PC、スマートフォンの管理
- セキュリティ教育:定期的な研修の実施
入管への届出に関する注意
届出が必要となる可能性のあるケース
以下の場合は、所属機関等に関する届出の検討が必要な場合があります
- • 勤務場所が契約上の事業所と大きく異なる場合
- • 常時在宅勤務で、実質的な勤務場所が変更となる場合
- • 業務内容や雇用条件に変更が生じる場合
※この判断は非常に専門的なため、個別のケースについては行政書士への相談を強く推奨します。
企業は、これらの対策を総合的に講じることで、外国人社員のリモートワークを適法かつ円滑に実施することができます。
7. 海外からのフルリモートワークは可能か?
技人国ビザを持つ外国人社員が、母国等の海外に居住したまま日本の企業の業務をフルリモートで行うことができるかという質問をよく受けますが、これについては慎重な検討が必要です。
技人国ビザの基本原則
技人国ビザは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」活動を対象としており、日本国内で活動することが前提となっています。単に日本の企業と契約しているだけでなく、日本を生活・活動の拠点とすることが求められます。
海外からのリモートワークが困難な理由
以下の理由により、海外居住でのフルリモートワークは技人国ビザの趣旨に適合しないと考えられます
- 活動場所の要件:在留資格は「日本に在留して行う活動」を許可するものであり、海外での活動は対象外
- 社会保険・税務:日本での社会保険加入、納税義務の履行が困難
- 労働法の適用:日本の労働基準法等の適用関係が不明確
- 指揮命令関係:海外居住での指揮命令関係の実効性に疑問
一時的な海外滞在は可能
ただし、以下のような一時的な海外滞在は問題ありません
許容される海外滞在例
- 出張:業務上必要な海外出張(数週間~数ヶ月程度)
- 帰省:年次有給休暇等を利用した母国への一時帰国
- 短期リモート:特定のプロジェクトでの短期間の海外からの業務
代替的なアプローチ
海外居住での日本企業との継続的な業務関係を希望する場合は、以下のような代替手段があります
- 業務委託契約:海外の個人事業主または法人として契約
- 海外支店・子会社:日本企業の海外拠点での雇用
- 特定活動ビザ:デジタルノマド制度等の活用
在留資格取消しのリスク
技人国ビザを持ちながら海外に長期滞在(目安として1年超)し、実質的に日本での活動を行っていない場合、「在留資格に該当する活動を継続して3月以上行わないで在留していること」を理由とした在留資格取消しの対象となる可能性があります。
海外からのリモートワークを検討する際は、技人国ビザの要件との整合性を慎重に検討し、必要に応じて専門家への相談を行うことを強く推奨します。
8. まとめ:適切な運用で、外国人社員の多様な働き方を実現
本記事では、技人国ビザを持つ外国人社員のフルリモートワーク・在宅勤務について、入管の基本的な考え方から企業が取るべき具体的な対策まで詳しく解説してまいりました。
重要なポイントの再確認
- 原則として可能:技人国ビザでのリモートワークは適切な管理の下で実施可能
- 業務実態が重要:専門的業務への従事と指揮命令関係の明確性が不可欠
- 日本が活動拠点:日本国内での居住と社会保険・納税が前提
- 適切な記録管理:業務内容、労働時間、成果物の体系的な管理
- 海外居住は困難:長期の海外滞在は技人国ビザの趣旨に反する
企業にとってのメリットと責任
適切に運用されたリモートワークは、企業と外国人社員の双方にメリットをもたらします
企業のメリット
- • 優秀な外国人人材の確保・定着
- • オフィスコストの削減
- • 生産性の向上
- • 多様性・包摂性の実現
外国人社員のメリット
- • ワークライフバランスの改善
- • 通勤時間の削減
- • 自律的な働き方の実現
- • 家族との時間の確保
しかし、これらのメリットを享受するためには、企業が法的責任を適切に果たすことが前提です。特に、外国人社員の在留資格に影響を与える可能性があることを十分に理解し、慎重な運用を心がける必要があります。
今後の展望
デジタル化の進展とともに、働き方の多様化はさらに進むと予想されます。入管当局も、時代の変化に応じた柔軟な運用を検討していく可能性がありますが、現時点では確立された基準に従った適法な運用が重要です。
最後に:専門家への相談の重要性
外国人社員のリモートワーク導入は、在留資格法、労働法、税務等の複合的な知識が必要な専門領域です。個別のケースによって対応が異なるため、実際の導入前には必ず行政書士等の専門家にご相談いただくことを強く推奨いたします。
適切な理解と準備により、外国人社員の多様な働き方を実現し、企業の競争力向上と社員の満足度向上の両立を図ってまいりましょう。
行政書士しかま事務所のリモートワーク導入コンサルティング
外国人社員のリモートワーク導入に関するお悩み、ございませんか?
当事務所がご支援できること
- 法的リスク評価:現在の運用状況における在留資格への影響評価
- 契約書・規程整備:外国人特有の注意点を踏まえた社内規程作成支援
- 運用体制構築:業務管理、記録保持、連絡体制の整備アドバイス
- 入管手続支援:必要な届出の判断と手続代行
- 継続的サポート:運用開始後のフォローアップとトラブル対応
こんなご相談をお受けしています
「外国人社員にフルリモートを認めても、ビザ更新で問題ないかチェックしてほしい」
「在宅勤務規程を整備したいが、外国人特有の注意点を教えてほしい」
「最新の入管運用について詳しく知りたい」
外国人社員の柔軟な働き方と企業のコンプライアンス
専門家が両立をサポートします
お気軽にご相談ください
行政書士しかま事務所 公式サイト※本記事の情報は2025年5月25日時点の法令・運用に基づくものです。入管法や関連法規は随時改正される可能性があり、個別の案件については具体的な状況に応じた判断が必要です。実際の手続きや運用については、必ず最新の法令を確認し、専門家にご相談ください。当事務所は記載内容の正確性には最大限注意を払っておりますが、本記事に基づく判断や行動による結果について一切の責任を負いかねます。
お気軽にお問い合わせください。03-6824-7297営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております