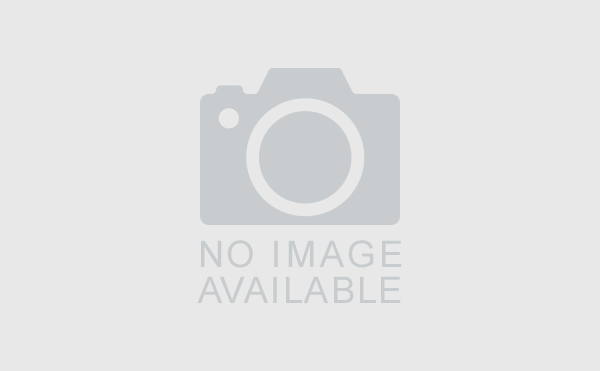「特定技能の外国人を採用したいが、登録支援機関はどう選べばいいのか?」
「月額2〜3万円という費用は適正なのか?安すぎる業者は危険なのか?」
「実績ゼロの機関に頼んでしまい、トラブルになることを避けたい」
このような不安を抱えている企業の担当者様は非常に多いです。特定技能の受入れにおいて、「登録支援機関」との契約は法律で定められた必須要件です。しかし、全国には約10,700機関(2025年11月現在)もの登録支援機関が存在し、その品質は玉石混交——。本記事では、ビザ申請の専門家である行政書士の視点から、信頼できる登録支援機関を選ぶための5つの実務的チェックポイントを徹底解説します。
はじめに:「特定技能」の必須パートナー。しかし、1万社からどう選ぶ?
特定技能の在留資格で外国人を受け入れる場合、企業には「義務的支援」と呼ばれる10項目の支援を提供する責任があります。これには、空港への送迎、住居の確保、携帯電話や銀行口座の開設同行、日本語学習の支援、3ヶ月に1度の定期面談など、外国人従業員の生活全般にわたる支援が含まれます。
しかし、多くの企業にとって、これらの支援を自社で完璧に実施することは現実的ではありません。そこで登場するのが「登録支援機関」です。登録支援機関は、企業に代わってこれらの支援業務を担う、いわば外国人従業員の「親」のような存在です。
問題は、全国に約10,700機関(2025年11月現在)もの登録支援機関が存在し、その品質がピンキリである点です。「どこに頼めばいいか分からない」「月額2〜3万円が適正価格か判断できない」——これが多くの担当者の本音ではないでしょうか。
この記事では、年間300件のビザ申請を手掛ける行政書士の視点から、「月額の支援費用をドブに捨てない」ための登録支援機関の見極め方をお伝えします。
そもそも「登録支援機関」の仕事とは?
登録支援機関の業務は、法律で定められた「10項目の義務的支援」を企業に代わって実施することです。具体的には以下のような支援が含まれます:
- 事前ガイダンス: 入国前に、労働条件や生活環境について説明する
- 出入国の送迎: 空港への迎えと帰国時の見送り
- 住居確保・生活に必要な契約支援: 住居の確保、携帯電話・銀行口座の開設同行
- 生活オリエンテーション: 日本の生活ルール、公共交通機関の利用方法などを説明
- 日本語学習の機会提供: 日本語教室の紹介や学習教材の提供
- 相談・苦情への対応: 母国語での相談対応(24時間体制が望ましい)
- 定期的な面談: 3ヶ月に1度、職場や生活の状況を確認
- 行政機関への同行: 必要に応じて役所や病院への同行
- 転職支援: 受入れ機関の都合により雇用契約を解除する場合(人員整理等)の転職先探しのサポート
- 定期報告: 入管への支援実施状況の報告
これらの支援は、外国人従業員が日本での生活に安心して順応し、長期的に定着するために不可欠です。登録支援機関は、単なる「書類作成業者」ではなく、「外国人従業員の生活を全面的にサポートするパートナー」である必要があります。
ポイント: 支援の質が低いと、外国人従業員の不満が溜まり、早期退職やトラブルに繋がります。だからこそ、登録支援機関選びは「コスト削減」だけでなく、「リスク管理」の観点から慎重に行うべきなのです。
失敗しないための「5つの選定チェックポイント」
それでは、具体的にどのような基準で登録支援機関を選べば良いのでしょうか。プロの視点から、以下の5つのチェックポイントを提示します。
① 専門性:「御社の業種」と「外国人の国籍」に対応しているか?
登録支援機関には、それぞれ得意分野があります。例えば、介護業界に強い機関、外食業に特化した機関、建設業に精通した機関など、業種によって専門性が異なります。また、外国人の国籍(母国語)への対応も重要です。
確認すべきポイント
- 業種のマッチング: あなたの会社の業種(例:建設、製造、外食、介護など)に対応した実績があるか
- 言語対応: 採用予定の外国人の母国語(例:ベトナム語、フィリピン語、中国語など)で支援できるか
- 地域の理解: 御社が所在する地域の特性(例:公共交通機関が少ない地方都市など)を理解しているか
検索のコツ: Googleで「登録支援機関 建設 フィリピン」のように、業種と国籍を組み合わせて検索すると、専門性の高い機関を見つけやすくなります。
なぜ重要か? 専門性のない機関に依頼すると、業界特有の課題(例:建設業の協議会加入、介護の研修制度)への対応が不十分になり、結果的にトラブルや不許可のリスクが高まります。
② 支援実態:「安かろう悪かろう」になっていないか?
登録支援機関の支援費用の相場は、月額2〜3万円程度です。しかし、業界には「契約だけして実際は何も支援しない」という"ゴースト機関"が存在します。また、極端に安い料金を提示する業者は、支援の質が伴わない「安かろう悪かろう」の典型である可能性が高いです。
"ゴースト機関"の罠
一部の登録支援機関は、契約だけして実際の支援は以下のようなものに限定されます:
- 3ヶ月に1度のオンライン面談のみ(実際の訪問や同行はゼロ)
- 緊急時の相談に応答しない(24時間対応と言いながら連絡が取れない)
- 住居確保や銀行口座開設の同行を「企業側でやってください」と丸投げ
これでは、企業が月額費用を払う意味がありません。外国人従業員も「誰も助けてくれない」と不満を募らせ、早期退職やトラブルに繋がります。
"価格の罠"
「月額1万円」「初期費用ゼロ」といった極端に安い料金設定の業者は要注意です。支援には人件費(訪問・同行・相談対応)がかかるため、適正価格を大幅に下回る場合、必ずどこかでコストカットが行われています。
対策:「物理的な近さ」を確認する
登録支援機関の事務所が、御社から車で30分〜1時間圏内にあるかをチェックしましょう。遠方の業者(例:東京の企業が沖縄の登録支援機関と契約)は、物理的に訪問が難しく、結果的にゴースト化しやすいのです。
まとめ: 適正価格(月額2〜3万円)を大きく下回る業者や、遠方の業者は避けるべきです。「安い=お得」ではなく、「安い=手抜き」である可能性を疑いましょう。
③ 実績:「本当に」支援を行っているか?
登録支援機関への登録には一定の基準がありますが、実際には「登録はしているが、支援実績が少ない、または支援が形骸化している」という機関が存在するとの指摘があります。
"登録だけ"の罠
入管の公式サイトには、登録支援機関のExcel名簿が公開されていますが、この名簿に載っているだけでは実績の有無は分かりません。名簿に掲載されている機関の中には、以下のようなケースが含まれます:
- 登録はしたが、実際に企業と契約した実績がない
- 契約実績はあるが、支援が形骸化している
- 他の本業(人材紹介、派遣など)のついでに登録しただけ
確認すべき質問
登録支援機関との面談時に、以下の質問を具体的に尋ねましょう:
- 「現在、何社の企業様と契約していますか?」
- 「現在、何名の外国人を支援していますか?」
- 「当社と同じ業種での支援実績はありますか?具体的な事例を教えてください」
- 「支援の中で最も多い相談内容は何ですか?」(実際に支援している機関なら、具体例をすぐに答えられます)
プロのアドバイス: 曖昧な回答(「複数社と契約しています」「守秘義務があるので…」など)しか返ってこない場合は要注意です。信頼できる機関は、具体的な数字や事例(匿名化した上で)を提示できるはずです。
まとめ: 入管の名簿に載っているだけでは信頼性は担保されません。実際の支援実績を数字と具体例で確認することが不可欠です。
④ サポート範囲:「協議会」の加入支援などもやってくれるか?
特定技能の受入れには、支援機関の支援業務だけでなく、すべての分野で「協議会」への加入が法律で義務付けられています(建設業、介護業、製造業、外食業など全12分野)。この協議会加入の手続きは複雑で、専門知識が必要です。
協議会加入が必要な分野(一部例示)
- 建設業: 建設分野特定技能協議会への加入が必須
- 介護業: 介護分野特定技能協議会への加入が必須
- その他: 製造業、宿泊業、外食業など、全12分野で協議会への加入が義務化されています
優良な登録支援機関は、支援業務に加えて、協議会加入の申請サポートも提供してくれる場合があります。これは法律で義務付けられた支援ではありませんが、企業にとっては非常に助かるサービスです。
確認すべき質問
- 「協議会への加入申請もサポートしていただけますか?」
- 「協議会加入に関する追加費用は発生しますか?」
- 「協議会からの定期報告や更新手続きもサポート範囲に含まれますか?」
ポイント: 登録支援機関が協議会加入までカバーしてくれる場合、企業側の負担が大幅に軽減されます。契約前に、「どこまでがサポート範囲か」を明確に確認しましょう。
まとめ: 単なる「10項目の支援」だけでなく、プラスアルファのサポート(協議会加入、入管への同行など)を提供してくれる機関は、企業にとって真のパートナーとなり得ます。
⑤【最重要】遵法性:「ビザ申請もやります」と言っていないか?
これは最も重要な警告です。一部の登録支援機関(株式会社や協同組合)は、「支援と一緒にビザ申請もセットでやります」という営業をしています。
これは完全に違法です!
在留資格(ビザ)の申請代行は、「行政書士法」および「入管法」により、行政書士と弁護士のみに許された独占業務です。登録支援機関(株式会社や組合)がビザ申請を行うことは、「非行政書士行為」として法律で禁止されています。
違法業者に依頼するリスク
- 不許可リスクの増大: 法律知識のない業者が申請すると、書類の不備や理由書の不適切な記載により、不許可になる可能性が高まります
- 企業側のコンプライアンス違反: 違法業者を利用した企業も、「適切な業者選定を怠った」として責任を問われる可能性があります
- 再申請の困難: 一度不許可になると、再申請のハードルが上がり、時間とコストが無駄になります
どう見分けるか?
登録支援機関との面談・契約時に、以下のような発言があった場合は即座に契約を見送るべきです:
- 「ビザ申請も一緒にやりますので、行政書士は不要ですよ」
- 「支援と申請をセットにすると割引になります」
- 「当社のスタッフが入管に申請しますので安心です」
正しい姿: 信頼できる登録支援機関は、「ビザ申請は行政書士の先生にお願いしてください。私たちは支援業務に専念します」と明確に線引きをしています。
まとめ: 「支援とビザ申請をセット販売」している業者は、違法業者である可能性が極めて高いです。企業のコンプライアンスとビザ許可の確実性を守るため、必ず「支援(登録支援機関)」と「申請(行政書士)」を分離させましょう。
「登録支援機関(支援)」と「行政書士(申請)」は、必ず"分離"させるべき
ここまで読んでいただいた方の中には、「当事務所(しかま事務所)は登録支援機関の業務もやっているのか?」と疑問に思われた方もいるかもしれません。
答えは「No」です。当事務所は、登録支援機関の業務を積極的には提供していません。その理由は、お客様の利益を最優先に考えた結果です。
それぞれの役割の違い
登録支援機関の仕事
- 業務内容: 外国人従業員の日常的な生活サポート(住居、銀行、相談、面談など)
- 契約形態: 月額の継続契約(通常、月額2〜3万円)
- 関係性: 長期的なパートナーとして、外国人従業員に寄り添う
行政書士の仕事
- 業務内容: 在留資格の申請・変更・更新などの法的手続き
- 契約形態: 1回限りのスポット契約(例:認定申請50,000円)
- 関係性: 専門的な法律知識を駆使し、入管へ確実に申請を通す
なぜ「分離」がお客様の利益になるのか?
もし当事務所が登録支援機関の業務も一緒に提供した場合、以下のような「抱き合わせ販売」のデメリットが発生します:
- 選択肢の制限: お客様は「ビザ申請はしかま事務所に頼みたいが、支援は別の機関が良い」という選択ができなくなる
- 支援の質が低下した場合の身動き: 支援の質に不満があっても、「ビザ申請もセットだから解約しづらい」という状況に陥る
- 利益相反のリスク: 支援業務で利益を上げるため、本来不要なサービスを提案してしまう可能性
当事務所の考え方:
お客様が「最高の登録支援機関」を自由に選び、当事務所が「最高のビザ申請サービス」を提供する——この独立した形が、お客様の利益に最もかなうと考えています。だからこそ、当事務所は登録支援機関の業務を積極的には行わず、ビザ申請の専門家として独立した立場を貫いています。
当事務所は、お客様が選んだ登録支援機関と直接連携し、スムーズに申請を進めます。支援と申請を分離することで、それぞれの専門性を最大限に活かすことができるのです。
まとめ:登録支援機関選びは「コスト」ではなく「リスク管理」
ここまで、登録支援機関を選ぶ際の5つのチェックポイントを解説してきました。最後に、もう一度重要なポイントをまとめます。
信頼できる登録支援機関を選ぶための5つの着眼点
- ① 専門性: 御社の業種と外国人の国籍に対応しているか
- ② 支援実態: 「安かろう悪かろう」になっていないか。物理的に近い機関か
- ③ 実績: 「登録だけ」でなく、実際の支援実績があるか
- ④ サポート範囲: 協議会加入などプラスアルファの支援があるか
- ⑤ 遵法性: 「ビザ申請もやります」という違法営業をしていないか
登録支援機関選びは、単なる「月額コストの比較」ではありません。外国人従業員の定着、企業のコンプライアンス、ビザ申請の成否を左右する「リスク管理」なのです。
上記の5つのポイントを必ずチェックし、真に信頼できるパートナーを選んでください。「安さ」だけで選んだ結果、支援が形骸化し、外国人従業員が早期退職してしまえば、採用コスト・教育コストがすべて無駄になります。
最終チェック: 契約前に、必ず登録支援機関の担当者と直接面談し、上記の質問をぶつけてみてください。その対応の誠実さ・具体性が、その機関の「本気度」を示します。
「登録支援機関」が決まったら、「ビザ申請」は当事務所にお任せください
信頼できる登録支援機関が決まりましたら、その後の最も複雑な「入管へのビザ申請」は、専門家である当事務所にお任せください。
当事務所は、お客様が選んだ登録支援機関と直接連携し、スムーズに申請を進めます。支援と申請を分離することで、それぞれの専門性を最大限に活かし、確実な許可を目指します。
特定技能VISA 認定・変更申請プラン
(税別・追加実費なし)
「月額の支援コスト(登録支援機関)」と「ビザ申請コスト(行政書士)」を明確に分離し、トータルコストを最適化したい企業様からのご連絡をお待ちしています。
無料相談はこちら免責事項
本記事の情報は2025年11月時点のものであり、法令の改正や制度の変更により内容が変更される場合があります。登録支援機関の選定は企業の責任において行うべきであり、本記事は選定基準の一例を示すものです。個別の状況については、必ず専門家(行政書士)にご相談ください。
また、本記事で紹介した業界の問題点(支援実態の欠如、違法な書類作成行為など)は、一般的な注意喚起を目的としており、特定の企業や団体を指すものではありません。登録支援機関の総数等のデータは、出入国在留管理庁の公式情報(2025年11月6日更新)に基づいています。