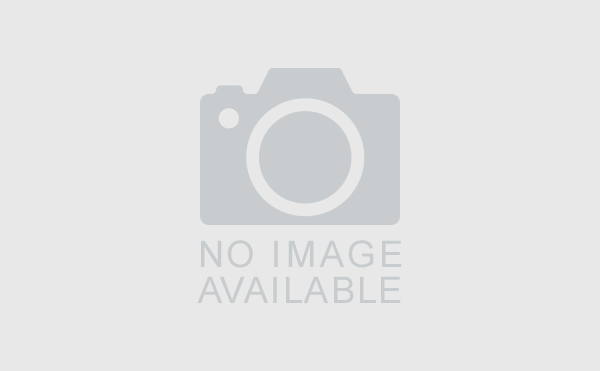特定技能の外国人を雇用している企業の皆様、毎月「登録支援機関」に支払っている支援委託料に、疑問を感じたことはありませんか?
出入国在留管理庁の調査(令和4年度)によると、月額委託費用の平均は1人あたり約28,386円、一般的な相場は1人あたり月額1.5万円〜3万円です。受入れ人数が増えるほど、このランニングコストは経営を圧迫します。
例えば、特定技能外国人を5人雇用している場合…
月額15万円、年間180万円
この費用、本当に適正でしょうか?
実は、この支援委託料を「ゼロ」にする方法があります。それが「自社支援」への切り替えです。
本記事では、年間300件規模のビザ申請を手掛ける行政書士の立場から、「自社支援」のメリット・リスク、そして最も賢い運用方法(ハイブリッド型)を徹底解説します。
目次
はじめに:「特定技能」1人あたり月額3万円。その費用、払い続けていませんか?
特定技能制度がスタートして以来、多くの企業が外国人材の受入れを「登録支援機関」に全面的に委託しています。
登録支援機関は、特定技能外国人に対する10項目の支援義務(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談など)を代行してくれる便利な存在です。しかし、その代償として企業は毎月、固定の委託料を支払い続けることになります。
一般的な相場は以下の通りです:
| 受入れ人数 | 月額委託料(@3万円の場合) | 年間コスト |
|---|---|---|
| 1人 | 3万円 | 36万円 |
| 3人 | 9万円 | 108万円 |
| 5人 | 15万円 | 180万円 |
| 10人 | 30万円 | 360万円 |
さらに、以下のような不満を抱えている企業も少なくありません:
- レスポンスが遅い:問い合わせをしても返信に数日かかる
- 形式的な面談:3ヶ月に1度の面談が、マニュアル通りの質問だけで終わる
- 個別対応の欠如:外国人スタッフの悩みや問題を早期に発見できていない
- コスト対効果の疑問:「本当にこの金額に見合うサービスなのか?」
このような状況に対し、「自社支援」という選択肢を検討してみませんか?
そもそも「自社支援」とは?
特定技能の受入れ企業(特定技能所属機関)には、外国人に対する10項目の支援義務が法律で定められています。
特定技能の10項目の支援義務とは?
- 事前ガイダンス(入国前または雇用契約締結後)
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション(日本のルール、公共交通機関の利用方法など)
- 公的手続き等への同行(市役所、銀行、病院など)
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(本人の都合により雇用契約を解除する場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報(3ヶ月に1回以上)
通常、これらの支援業務は登録支援機関に委託されます。しかし、法律上、企業が自ら支援を行う(自社支援)ことも完全に認められています。
「自社支援」とは…
登録支援機関に頼らず、受入れ企業が自らの責任で、上記10項目の支援を実施すること。これにより、登録支援機関への月額委託料は一切不要になります。
ただし、自社支援を行うためには一定の要件(支援責任者・支援担当者の選任、過去2年以内の中長期在留者の雇用実績、外国語対応能力など)を満たす必要があります。
メリット:「自社支援」に切り替える最大の理由
では、なぜ今、多くの企業が「自社支援」への切り替えを検討しているのでしょうか?主なメリットは以下の通りです。
① 圧倒的なコスト削減
これが最大の理由です。月額1.5〜3万円×人数分のランニングコストがゼロになります。例えば5人雇用なら年間180万円、10人なら年間360万円のコスト削減効果です。ビザ申請を専門家に依頼しても「申請時のみ」の費用であり、トータルコストは劇的に下がります。
② サポート品質の向上
登録支援機関の形式的な面談とは異なり、自社の人事担当者や上司が直接、外国人スタッフとコミュニケーションを取ることで、真の問題(人間関係、業務の悩み、体調不良など)を早期に発見・解決できます。結果的に離職率の低下にも繋がります。
③ ノウハウの社内蓄積
外国人サポートのノウハウが社内に蓄積され、企業のダイバーシティ推進や、今後の更なる受入れ拡大の基盤となります。これは、企業の長期的な競争力に繋がる無形資産です。
④ 柔軟で迅速な対応
登録支援機関を介さないため、緊急時(病気、トラブル、住居問題など)に即座に対応できます。外部機関との連絡待ちがなくなり、スピーディーな問題解決が可能になります。
特にコスト削減の効果は絶大です。受入れ人数が増えれば増えるほど、自社支援への切り替えによる削減額は大きくなります。
リスク:「自社支援」の前に知るべき"2つの壁"
しかし、メリットだけを見て安易に切り替えることは危険です。自社支援には、見落としがちなリスクが潜んでいます。
自社支援に伴う主要リスク
リスク①:支援体制の構築と「支援担当者」の任命
自社支援を行うには、以下の体制整備が法律で義務付けられています:
- 支援責任者の選任:支援業務全体を統括する役員または職員
- 支援担当者の選任(各事業所に1名以上):外国語(英語、ベトナム語、中国語など)での対応が可能な常勤の職員
- 過去2年以内の実績:中長期在留者(就労ビザを持つ外国人)の雇用または管理の実績
- 支援責任者・支援担当者の要件:過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験
「3ヶ月に1度の定期面談」や「相談窓口の設置」など、法律で定められた支援を「確実に」実行できる社内リソース(人手、時間、体制)が必要です。
リスク②:法令遵守と「支援計画書」の不備
これが最重要リスクです。自社支援が「支援義務の不履行」と判断された場合(例:面談を忘れた、報告書を提出しなかった、支援計画書に不備があった)、以下のペナルティが科されます:
- 入管当局からの改善命令(是正指導)の対象となる
- 改善命令に従わない場合:6月以下の懲役または30万円以下の罰金(入管法第71条の3)
- 悪質な場合:特定技能外国人の受入れ停止処分(最大5年間)
- 現在雇用中の特定技能外国人も、在留資格の更新が認められない可能性
- 企業名の公表
つまり、自社支援の失敗は、企業の外国人雇用ビジネスそのものを崩壊させるリスクを持っています。
特に、法令遵守(コンプライアンス)は、多くの企業が軽視しがちなポイントです。「面談をやっているつもり」「記録は残していない」といった"なんとなく"の対応では、入管の監査で指摘を受ける可能性があります。
最大のリスクは「ビザ申請」の自社対応
そして、自社支援に切り替えた企業が最も見落とすのが、「ビザ申請業務」の専門性です。
※重要な補足:法律上、登録支援機関の業務は「10項目の義務的支援」が中心であり、ビザ申請業務(在留資格認定・変更・更新申請)は登録支援機関の法定業務には含まれていません。ただし、実務上は多くの登録支援機関が提携する行政書士にビザ申請を委託し、その費用を月額料金に含めているケースが一般的です。
自社支援に切り替えると、この最も専門的で複雑な「ビザ申請」も、自社で行うか、別途行政書士に依頼する必要があります。
ビザ申請を素人が行うリスク
- 書類不備による不許可:必要書類の漏れ、フォーマットの誤りなど
- 支援計画書の不備:入管が最も重視する「支援計画書」の記載ミス(これが原因で不許可になるケースが多発)
- 審査の長期化:不備があると、補正→再提出→追加資料要求…と、審査が数ヶ月遅延
- 不許可時の再申請コスト:一度不許可になると、再申請はさらに難易度が上がる
- 外国人の不安とモチベーション低下:「この会社、大丈夫か?」と信頼を失う
重要なポイント
「日常の支援(面談、生活サポート)」は自社でできても、「ビザ申請(法的手続き)」は別次元の専門業務です。ここを混同すると、自社支援は失敗します。
特に、特定技能の「支援計画書」は、入管審査の最重要書類です。ここに不備があれば、どんなに優秀な外国人材でも、どんなに真面目に支援していても、ビザは下りません。
結論:最強の体制は「自社支援(サポート)」+「行政書士(ビザ申請)」
当事務所が推奨する最適解では、企業はどうすべきか?答えはシンプルです。「ハイブリッド型」の運用です。
最も賢い特定技能の運用体制
日常の支援(10項目の義務)
自社支援で対応
- 定期面談(3ヶ月に1回)
- 生活サポート(病院同行、役所手続き支援など)
- 相談窓口の運営
- 日本語学習支援
→ 登録支援機関への月額費用ゼロ
ビザ申請業務(法的手続き)
専門家(行政書士)に外注
- 在留資格の変更申請
- 在留資格の更新申請
- 支援計画書の作成・チェック
- 入管との折衝・補正対応
→ 申請時のみの費用(月額不要)
この体制なら、以下のすべてのメリットを享受できます:
- 圧倒的なコスト削減:登録支援機関に支払っていた月額のランニングコストがゼロに
- サポート品質の向上:自社で直接、外国人スタッフの状況を把握できる
- ビザ申請の安全性:最も不許可リスクが高い「ビザ申請」は、専門家に任せて確実に許可を取る
- 法令遵守(コンプライアンス):支援計画書など、入管提出書類は行政書士がチェックするため、法令違反のリスクを最小化
トータルコストの比較例(特定技能5人の場合)
| パターン | 年間コスト |
|---|---|
| 登録支援機関全面委託(月額3万円×5人) | 約180万円 |
| 自社支援+行政書士(ビザ更新:5万円×5人×年1回) | 約25万円 |
| 削減額 | 約155万円/年 |
※上記は更新申請のみの費用試算です。新規受入れ時の認定申請・変更申請は別途費用が発生します。詳細は個別にお問い合わせください。
このように、「自社支援+行政書士」の体制は、コスト削減と安全性(法令遵守)を両立させる、最も賢い選択肢なのです。
「自社支援」へ切り替える企業様、ビザ申請は当事務所にお任せください
行政書士しかま事務所
特定技能ビザ申請プラン
当事務所は、年間300件規模のビザ申請実績を持つ、特定技能ビザのプロフェッショナルです。「自社支援」に切り替えた企業様にとって、最適なパートナーです。
当事務所が選ばれる3つの理由
- ① 圧倒的な低コスト:特定技能ビザ申請50,000円〜(税別、申請内容により異なる)。登録支援機関の月額費用と比べ、トータルコストを劇的に削減できます。
- ② DXによる効率化:オンライン完結型の申請サポート。書類のやり取りはすべてクラウドで完結し、企業様(支援担当者様)の手間を最小限に抑えます。
- ③ 「支援計画書」作成のプロ:入管審査の最重要書類である「支援計画書」の作成・チェックは、年間300件規模の実績を持つ当事務所にお任せください。法令に準拠し、かつ審査をパスできる完璧な書類を作成します。
「月額コストの削減」と「ビザ申請の法令遵守」を両立させたい企業様、
まずは無料相談でお話をお聞かせください。
※初回相談は完全無料。オンライン(Zoom等)または電話でのご相談も可能です。
まとめ:自社支援は「コスト削減の切り札」、だが「ビザ申請」は専門家に
本記事でお伝えした内容を、改めて整理します:
- 登録支援機関への月額委託料(@1.5〜3万円)は、ランニングコストとして重い。受入れ人数が増えるほど、年間数十万円〜数百万円の固定費になる。
- 「自社支援」は、このコストをゼロにできる合法的な方法。法律で認められた正式な選択肢であり、登録支援機関への委託は義務ではない。
- 自社支援のメリットは「コスト削減」「サポート品質向上」「ノウハウ蓄積」。特にコスト削減効果は絶大。
- しかし、支援体制の構築と法令遵守(コンプライアンス)のリスクがある。特に「支援義務の不履行」は、改善命令・罰則・受入れ停止という重大なペナルティに繋がる。
- 最大のリスクは「ビザ申請」を自社で行うこと。書類不備、支援計画書の不備で不許可になるケースが多発。
- 最適解は「自社支援(日常サポート)」+「行政書士(ビザ申請)」のハイブリッド型。これにより、コスト削減と安全性を両立できる。
「自社支援」への切り替えは、企業にとって大きなコスト削減のチャンスです。しかし、その一方で、ビザ申請という専門業務を軽視してはいけません。
当事務所は、「自社支援」に挑戦する企業様を、低コストで、かつ確実にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
免責事項
情報の正確性について:本記事の内容は、2025年11月時点の出入国在留管理庁の公表資料および運用に基づいています。法改正や運用変更により、内容が変更される可能性があります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
自社支援の要件について:「自社支援」を実施するには、過去2年以内の中長期在留者の雇用実績、支援責任者・支援担当者の選任、外国語対応能力など、法令で定められた要件を満たす必要があります。すべての企業が実施できるわけではありません。
費用について:記事内に記載された費用はあくまで一般的な相場や当事務所の参考価格であり、個別の案件の内容(申請の種類、書類の複雑さ、企業の状況など)により変動します。正式なお見積もりは個別にお問い合わせください。
登録支援機関とビザ申請業務について:法律上、登録支援機関の業務範囲は「10項目の義務的支援」が中心であり、ビザ申請業務は法定業務に含まれません。ただし、実務上は提携する行政書士にビザ申請を委託し、その費用を含めたパッケージで提供している登録支援機関も存在します。
免責:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言を構成するものではありません。実際の自社支援への切り替えやビザ申請については、必ず専門家(行政書士)にご相談ください。本記事の情報に基づいて行った行為により生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いかねます。
この記事に関するご質問・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
無料相談を予約する