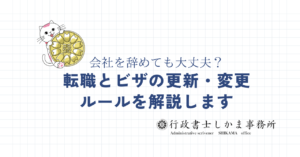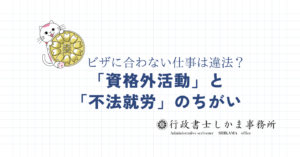外国人従業員の社会保険・労災・雇用保険の適用ルールまとめ
はじめに
こんにちは。行政書士しかま事務所です。当事務所では、在留資格申請を中心に、外国人雇用に関する様々な手続きのサポートを行っています。
近年、日本で働く外国人の数は年々増加しており、企業の人事担当者様からは「外国人従業員の社会保険や労働保険はどうすればよいのか」というご質問を多くいただきます。また、外国人の方々からも「日本の保険制度について知りたい」という声をよく耳にします。
大原則
外国人従業員の保険加入義務は「国籍」ではなく「働き方(雇用条件)」で決まります
この記事では、外国人従業員に対する以下の保険の適用ルールと加入手続きについて、わかりやすく解説します。
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)
- 労災保険(労働者災害補償保険)
- 雇用保険
この記事を読むことで、企業の人事担当者様は適切な加入手続きを行う際の参考に、また外国人従業員の方々は自分の権利について理解を深めることができるでしょう。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
どんな保険か?
社会保険は、主に「健康保険」と「厚生年金保険」の2つから構成されています。
- 健康保険:病気やケガをした際の医療費を保障(通常3割負担で医療サービスを受けられる)
- 厚生年金保険:老後の年金受給権を確保するための制度
加入対象者(誰が入るか?)
原則として、以下の条件を満たす従業員は国籍を問わず社会保険の加入対象となります。
正社員の場合
適用事業所(法人または常時従業員5人以上の個人事業所など)で常時雇用される従業員は、加入義務があります。
パート・アルバイトの場合
以下の要件をすべて満たす場合、加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれる
- 学生でないこと(一部例外あり)
※2024年10月〜従業員51人以上の企業が対象となります。※従業員:厚生年金保険の被保険者数
手続き
社会保険の加入手続きは、原則として会社(事業主)が行います。入社後5日以内に、年金事務所または健康保険協会へ「資格取得届」を提出します。保険料は労使折半で、給与から従業員負担分が控除されます。
外国人向けのポイント
脱退一時金制度について
厚生年金に6ヶ月以上加入していた外国人の方が、年金受給権を得ずに日本を出国する場合、出国後2年以内に請求することで、支払った厚生年金保険料の一部が返還される「脱退一時金」制度があります。詳細は日本年金機構のウェブサイトで確認できます。
労災保険(労働者災害補償保険)
どんな保険か?
労災保険は、従業員が仕事中や通勤中のケガ・病気などで被った損害を補償する保険です。具体的には以下のような補償があります。
- 業務上または通勤中の傷病に対する医療費(全額補償)
- 休業補償(休業4日目から、給付基礎日額の80%)
- 障害が残った場合の障害補償
- 遺族への補償、葬祭料など
加入対象者(誰が入るか?)
労災保険は、雇用形態(正社員、パート、アルバイト等)や国籍、在留資格に関わらず、日本国内で働く基本的にすべての労働者が対象です。
つまり、以下の条件をすべて満たす方は、外国人であっても労災保険の対象となります
- 日本国内の事業所で働いている
- 事業主との間に使用従属関係がある(指揮命令下で働いている)
在留資格が「留学」であっても、アルバイト(資格外活動)として働く場合は対象となります。また、「技能実習」「特定技能」などの在留資格の方も当然対象です。
ポイント
- 1人でも労働者を雇っていれば、事業主は加入義務があります
- 保険料は全額事業主負担です(労働者の負担なし)
- 労災保険は、不法就労者であっても適用されます(ただし不法就労自体は法律違反です)
雇用保険
どんな保険か?
雇用保険は、失業した場合の給付(失業保険)や、育児休業・介護休業中の給付などを行う制度です。主な給付内容は以下の通りです。
- 求職者給付(いわゆる失業保険)
- 育児休業給付
- 介護休業給付
- 教育訓練給付 など
加入対象者(誰が入るか?)
以下の要件を満たす従業員は、原則として国籍を問わず雇用保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
注意点
在留資格による対象外のケース
在留資格の種類によっては、雇用保険の対象外となる場合があります。
例えば
- 留学生の資格外活動(アルバイト)は原則として対象外
- 家族滞在の方のアルバイトも原則として対象外
- 特定活動(ワーキングホリデー)も原則として対象外
※ただし上記でも、本来の在留資格の活動を行っていない実態がある場合などは、個別判断となります。
手続き
雇用保険の加入手続きは、会社(事業主)が行います。入社後、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。保険料は労使双方が負担します(労働者負担分は給与から控除)。
企業(事業主)の主な義務まとめ
加入義務
- 各保険の適用条件を確認し、対象となる従業員(外国人含む)を適切に加入させる義務
- 社会保険は入社後5日以内、雇用保険は入社後10日以内に届出
- 労災保険は事業開始と同時に自動的に適用されるが、新規事業開始時は労働基準監督署への届出が必要
保険料の計算・納付
- 社会保険・雇用保険:労使双方の負担(給与から従業員負担分を控除)
- 労災保険:全額事業主負担
外国人雇用状況の届出
外国人を雇用する場合、雇入れ・離職の際には「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出する義務があります(雇入れ・離職の日から2カ月以内)。これは、保険加入の有無にかかわらず必要な手続きです。
まとめ
外国人従業員の社会保険・労働保険の適用について、ポイントをまとめます。
- 外国人従業員も日本人従業員と同様に、働き方(雇用条件)によって保険の適用対象となるかが決まります。国籍や在留資格だけで一律に判断するものではありません。
- ただし、在留資格によっては雇用保険の適用が除外される場合があります(留学生のアルバイトなど)。
- 労災保険は、雇用形態や国籍、在留資格に関わらず基本的にすべての労働者が対象です。
- 企業は適切な保険加入手続きを行う法的義務を負います。これはコンプライアンス上だけでなく、従業員が安心して働ける環境作りの観点からも重要です。
外国人従業員にとっても、日本の保険制度を理解することで、安心して働き、必要な場面で適切な保障を受けることができます。特に健康保険は医療費の負担を大きく軽減できるメリットがありますので、加入条件を満たしている場合は必ず加入することをお勧めします。
個別のケースについては専門家へのご相談を
この記事では、外国人従業員の社会保険・労働保険の基本的な適用ルールについて解説しましたが、実際の現場では様々な状況があり、判断が難しいケースも少なくありません。
- 「うちの会社のケースではどうなるのか?」
- 「この従業員は加入要件を満たすのか?」
- 「在留資格の変更に伴う保険の手続きはどうすればよいのか?」
このような個別のケースについては、専門家への相談が確実な方法です。
行政書士しかま事務所へのご相談
当事務所では、在留資格申請のサポートに加え、外国人雇用に関する労務管理(社会保険・労働保険の加入手続きを含む)のご相談にも対応しております。
不明点やお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。03-6824-7297営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております