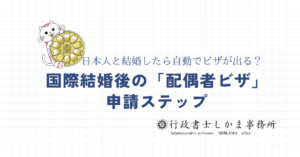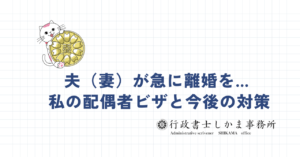空き家活用ビジネスを後押し!「小規模事業者持続化補助金」活用術
空き家活用ビジネスを後押し!
行政書士と狙う「小規模事業者持続化補助金」活用術
2025年5月時点の最新情報に基づく、空き家活用事業者のための補助金活用ガイド
はじめに: 空き家活用の可能性と、それを現実にする補助金
こんにちは、行政書士しかま事務所です。当事務所では、事業者の皆様のビジネス展開をサポートするため、各種許認可申請から補助金申請まで、幅広くサポートを行っています。
日本全国で急増している空き家。総務省の2023年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家数は900万戸に達し、空き家率は13.8%と過去最高を記録しました。これは、およそ7.2軒に1軒が空き家という状況です。

図1: 空き家数及び空き家率の推移—全国(1978年~2023年)[出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」]
しかし、この状況は見方を変えれば、新たなビジネスチャンスともいえます。空き家の有効活用は、地域活性化や新たな価値創造につながるだけでなく、資源の有効活用という社会的意義も持っています。カフェ、宿泊施設、シェアオフィス、教室、工房など、さまざまな形で空き家を再生し、新しいビジネスを始める事業者が増えているのです。
ただし、空き家の改修や活用には初期費用という大きな壁があります。そこで力強い味方となるのが、国や自治体による「補助金」制度です。特に、個人事業主や小規模事業者にとって身近な「小規模事業者持続化補助金」は、空き家を活用したビジネス展開に理想的な支援制度と言えるでしょう。
本記事では、小規模事業者持続化補助金を中心に、空き家活用ビジネスで利用できる補助金制度と、その申請のポイントについて詳しく解説します。また、私たち行政書士がどのようにサポートできるのかについても説明します。
空き家問題の実態と所有者の状況を理解する
まず、空き家の取得経緯と所有者の実態について見てみましょう。下記のデータは、空き家活用ビジネスを考える上で重要な視点を提供してくれます。

図2: 空き家の取得経緯・所有者と空き家の距離関係・所有者の年齢[出典:国土交通省 空き家所有者実態調査]
空き家の取得経緯
空き家の55%近くが「相続」によって取得されています。つまり、計画的に取得したものではなく、突然所有者となったケースが多いのです。ここに、空き家活用の大きな障壁がある一方、ビジネスチャンスも潜んでいます。
所有者の特徴
空き家所有者の6割以上が65歳以上の高齢者です。また、所有者が徒歩圏内に住んでいるケースが35.6%ある一方、車で3時間以上離れた場所に住む所有者も12.5%存在します。こうした状況も、空き家が活用されにくい要因となっています。
さらに、空き家所有者の今後の利用意向についても確認しておきましょう。

図3: 空き家の将来の利用意向と活用活動の状況[出典:国土交通省 空き家所有者実態調査]
重要ポイント
- 所有者の約20%以上が「賃貸・売却意向」を持っている
- 賃貸・売却に向けた活動をしている所有者のうち、約40%が「募集中」の状態
- 約30%の所有者が「空き家にしておく意向」を持っている
これらのデータは、空き家を活用したビジネスを展開する上で、どのような物件にアプローチすべきか、どのような所有者が協力的な可能性が高いかを考える手がかりになります。特に「売却・賃貸意向を持ちながらも活動していない」層は、適切なサポートがあれば空き家活用に前向きになる可能性があります。
なぜ「空き家活用」に補助金が使えるのか?なぜ行政書士が関与するのか?
空き家問題は単なる個人資産の問題ではなく、地域社会全体に関わる社会課題となっています。総務省の調査によれば、全国の空き家数は2023年時点で900万戸に達し、総住宅数の13.8%を占めるに至りました。このまま放置すれば、2033年には1,500万戸(約20%)に達するとの予測もあります。
こうした状況を背景に、国や自治体は空き家の有効活用を推進するため、さまざまな補助金制度を設けています。これには主に以下のような政策目的があります
地域活性化
空き家を活用した新たなビジネスは、地域に賑わいや雇用を創出します
景観維持・防犯対策
適切に管理・活用された空き家は、街の安全性や美観の向上に貢献します
新規創業促進
空き家活用は、創業コスト削減につながり、新規事業者の参入を促進します
また、多くの補助金は「単なる資金援助」ではなく、「事業計画の実現性や将来性」を審査対象としています。つまり、「お金がほしい」という理由だけでは採択されません。地域に価値を生み出し、持続可能なビジネスモデルを構築する計画であることが求められるのです。
ここで行政書士の専門性が生きてきます。私たち行政書士は、
- 事業計画の策定支援と、その計画を補助金審査員に効果的に伝えるドキュメント作成
- 空き家活用に必要な各種許認可申請(飲食店営業許可、民泊届出、古物商許可など)
- 法令遵守(コンプライアンス)の観点からのアドバイス
といった専門的なサポートを提供できます。空き家活用ビジネスでは、単に改装して事業を始めるだけでなく、さまざまな法的手続きや計画策定が必要になります。行政書士はこれらをワンストップでサポートする「事業の伴走者」となるのです。
大本命!「小規模事業者持続化補助金」を空き家活用ビジネスに最大限活かす方法
制度概要(2025年5月最新情報)
目的:小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取り組みを支援
対象者:商業・サービス業で従業員5人以下、製造業・その他の業種で従業員20人以下の事業者
補助上限額:通常枠で50万円(特例適用で最大250万円)
補助率:補助対象経費の2/3(賃金引上げ特例の赤字事業者の場合は3/4)
最新公募回:第17回公募(2025年6月13日締切)
主な変更点:住宅宿泊事業者の改装費用について、事業用部分の面積按分が認められるようになりました
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2025年3月4日 |
| 申請受付開始 | 2025年5月1日 |
| 申請受付締切 | 2025年6月13日 17:00 |
| 事業支援計画書締切 | 2025年6月3日(商工会・商工会議所への相談は余裕をもって) |
| 補助事業実施期間 | 交付決定日から2026年7月31日まで |
| 実績報告書締切 | 2026年8月10日 |
空き家活用ビジネスでの具体的な「補助対象経費」例
小規模事業者持続化補助金では、主に以下の8種類の経費が補助対象となります。空き家活用ビジネスに特に関係の深い経費例をご紹介します。
①機械装置等費
- カフェ開業のためのコーヒーマシン、製氷機
- 工房開設のための工作機械、3Dプリンター
- 宿泊施設のための業務用洗濯機、乾燥機
- 店舗用の冷蔵庫、エアコン、空気清浄機
※汎用性の高いパソコン、プリンター、家具等は基本的に対象外となるため注意が必要です
②広報費
- 新規オープン告知のチラシ・ポスター制作費
- 店舗や施設の看板の製作・設置費
- 地元メディアへの広告掲載費
- 商品・サービスを紹介するパンフレット製作費
※単なる会社案内や求人広告等は対象外です
③ウェブサイト関連費
- 空き家を活用した店舗・施設のホームページ制作
- 予約システムの構築費用
- オンラインショップの開設費用
- SNS広告、地域特化型のWeb広告費
※ウェブサイト関連費のみの申請はできません。上限額は交付申請額の1/4です
⑦借料
- 空き家を賃借して店舗等として使用する場合の賃料
- イベント開催時の会場借料
- 事業に必要な機器・設備のリース料
※既存の事務所等の賃料は対象外です。新たな販路開拓の取り組みとして空き家を借りる場合のみ補助対象となります
【住宅宿泊事業者の改装費用按分について】
第17回公募より、住宅宿泊事業者(民泊)が空き家を改装する場合、「住宅のうち事業の用に供する部分の面積」により按分した金額が補助対象となりました。
たとえば、借りた空き家の総面積が100㎡で、そのうち60㎡を宿泊用として使用し、残り40㎡を居住用として使用する場合、改装費用の60%のみが補助対象となります。
必要な提出書類
- 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書の写し
- 計算根拠となる平面図等(事業用部分の面積が明示されたもの)
※これらの書類は採択後、交付決定までの間に提出する必要があります
⑧委託・外注費 — 空き家改装の強い味方
空き家活用ビジネスで最も活用価値が高いのが「委託・外注費」です。特に以下のような経費が補助対象となります
- 店舗改装・バリアフリー化工事
- 利用客向けトイレの改装工事
- 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
- 空き家の断熱改修、省エネ対策工事
- Wi-Fi環境構築、セキュリティシステム設置
- 看板や照明の設置工事
- 従業員の作業導線改善のための間仕切り工事
- 顧客動線を考慮した店舗レイアウト変更
補助対象外となる主な経費
- 単に古くなった設備の取替えや修繕
- 住居と店舗の併用物件で、住居部分の改装費用
- 不動産の取得費(空き家の購入費用)
- 消耗品の購入費
- 家賃や光熱水費などの経常的経費
- 補助事業期間外に実施した工事や支払い
採択の最重要ポイント:「経営計画書」と「補助事業計画書」の質
小規模事業者持続化補助金の採択を勝ち取るには、魅力的な事業計画書の作成が不可欠です。特に空き家活用ビジネスでは、以下の点を明確に示すことが重要です
経営計画書で示すべきポイント
- なぜその空き家を選んだのか(立地の強み)
- 地域ニーズとの合致点(地域活性化への貢献)
- あなたの強み・経験と事業内容の関連性
- 競合との差別化ポイント
- 中長期的な事業展望
補助事業計画書で示すべきポイント
- 空き家活用によって実現する新たな販路や顧客層
- 補助金で導入する設備や実施する工事の具体的効果
- 事業実施スケジュールの現実性
- 収支計画の妥当性
- 費用対効果の高さ
行政書士による支援は、これらの計画書作成において大きな力となります。私たち行政書士は、多くの申請支援経験から「採択される計画書」のポイントを熟知しています。また、空き家活用に際して必要な許認可についても併せてアドバイスできるため、計画の実現可能性を高めることができます。
他にもある!行政書士がサポートしやすい「空き家×事業」関連の補助金・制度例
小規模事業者持続化補助金以外にも、空き家活用ビジネスに活用できる補助金・助成金が多数あります。代表的なものをご紹介します。
各自治体の「創業支援補助金」「起業家支援補助金」
空き家を活用して新規事業を始める場合に利用できることが多い補助金です。地域の産業振興や雇用創出に貢献する事業が対象となります。
補助額例: 30万円~300万円程度(自治体により異なる)
行政書士の関与ポイント
- 法人設立手続きや個人事業開始手続きと併せたトータルサポート
- 地域貢献性をアピールする事業計画書の作成支援
「空き家活用推進事業補助金」(国交省・自治体)
空き家を改修して住宅や店舗等として再生する際の費用を補助する制度で、各自治体が独自の条件を設定しています。
補助額例: 改修工事費の1/3程度(上限100万円~300万円)
行政書士の関与ポイント
- 自治体によって異なる申請条件の整理と最適な制度の選定
- 関連する建築確認申請等の行政手続きのコーディネート
空き家を活用した特定の事業に対する自治体独自の補助金
地域交流拠点、福祉施設、子育て支援施設、観光施設など、自治体が推進する特定用途での空き家活用に対する補助金です。
補助額例: 事業内容により大きく異なる(数十万円~数千万円)
行政書士の関与ポイント
- 事業に必要な許認可申請と補助金申請の一体的サポート
- 地域課題解決型の事業計画策定支援
省エネ・脱炭素関連の改修補助金
空き家の断熱改修やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化、再生可能エネルギー設備の導入などに利用できる補助金です。
補助額例: 工事費の1/3~2/3(条件による)
行政書士の関与ポイント
- 複数の補助金の組み合わせによる最適活用の提案
- SDGs・環境配慮型ビジネスとしての事業計画策定支援
これらの補助金は地域や時期によって内容や募集状況が異なります。また、複数の補助金を組み合わせて活用できる可能性もあります(ただし、同一の経費に対して重複して補助を受けることはできません)。最新の情報と、ご自身の事業に最適な補助金については、ぜひ当事務所にご相談ください。
行政書士に「空き家活用補助金」の申請サポートを依頼する具体的なメリット
補助金制度の最適選定
多種多様な補助金の中から、あなたの空き家活用計画に最適な制度を選定します。小規模事業者持続化補助金だけでなく、自治体独自の制度や他の国の補助金も含めて、最も有利な申請方法を提案します。
採択率を高める事業計画書作成
数多くの申請支援実績から得た知見を活かし、審査員の視点を理解した事業計画書を作成します。特に「なぜその空き家なのか」「地域にどんな価値を生み出すのか」といった審査ポイントを押さえた計画書づくりをサポートします。
複雑な手続きの正確な実行
Gビズ IDの取得から電子申請システムの操作、商工会・商工会議所との連携など、煩雑な手続きを的確に進めます。提出書類の不備によるリスクを最小化し、スムーズな申請をサポートします。
本業への集中を可能に
補助金申請は非常に時間と労力を要する作業です。申請書類の作成から提出までをプロに任せることで、あなたは本業やビジネスの準備に集中できます。特に空き家活用ビジネスの立ち上げ期は、設備の選定や内装の検討など、やるべきことが山積みです。その貴重な時間を守ります。
関連許認可申請とのワンストップ対応
行政書士の最大の強みは、補助金申請と関連許認可申請を一体的に進められること。空き家活用ビジネスでよく必要となる許認可(飲食店営業許可、民泊届出、古物商許可、酒類販売免許の申請サポートなど)と補助金申請を、整合性を取りながら同時に進めることができます。
「申請書類の作成が難しそう」「自分だけで準備すると採択されるか不安」「本業が忙しくて時間がない」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家のサポートを検討してみてください。特に新規事業として空き家活用を考えている場合、初期費用を大きく軽減できる補助金は、ビジネスの成功に大きく貢献します。
補助金申請準備の一般的な流れと心構え
小規模事業者持続化補助金の申請から採択までの流れ
情報収集と事業構想の具体化
空き家活用のアイデアを具体化し、必要な設備や改装内容、提供するサービス・商品を明確にします。この段階で行政書士に相談することで、実現可能性の高い計画づくりができます。
GビズIDプライムの取得
電子申請に必要なGビズIDの取得は2~3週間かかります。公募開始前から準備しておくことをお勧めします。
商工会・商工会議所への相談
小規模事業者持続化補助金には「事業支援計画書」が必須です。地域の商工会・商工会議所に早めに相談し、計画内容への助言をもらいながら進めます。
経営計画書・補助事業計画書の作成
事業の具体的な内容、市場分析、販路開拓策、資金計画などを盛り込んだ計画書を作成します。行政書士のサポートにより、採択率の高い計画書に仕上げます。
申請書類の提出
電子申請システムで必要書類をすべて提出します。住宅宿泊事業者が改装費用を計上する場合は、届出書や面積按分の根拠資料も準備します。
審査と採択
提出から約2~3ヶ月後に採択発表があります。採択されたら、交付申請の手続きを経て、補助事業を開始します。
申請の心構え
余裕を持ったスケジュール管理
締切直前は申請システムが混雑し、トラブルが発生しやすくなります。少なくとも締切の1週間前には申請を完了させることを目指しましょう。特に事業支援計画書の発行は締切の10日前までに依頼するのが安心です。
「審査員目線」で計画書を作成
補助金は「もらえるもの」ではなく「事業計画に基づいて勝ち取るもの」です。審査員は「この事業が成功する確率はどれくらいか」「地域や社会にどんな価値を生み出すか」という視点で審査します。第三者に読んでもらい、説得力をチェックしてもらうことも有効です。
住宅宿泊事業(民泊)で空き家活用を考えている方へ
2025年の第17回公募から、住宅宿泊事業者の改装費用について、事業用部分の面積按分が認められるようになりました。これにより、空き家を改装して民泊を始める際の費用負担を大きく軽減できます。
ただし、以下の点に注意が必要です
- 住宅宿泊事業法に基づく届出が必要
- 住宅のうち事業用部分と住居部分の明確な区分け
- 面積按分の根拠となる平面図の準備
行政書士しかま事務所では、住宅宿泊事業法の届出から補助金申請まで一貫してサポートしています。空き家を民泊として活用したい方は、ぜひご相談ください。
まとめ:補助金は空き家ビジネスの起爆剤、専門家と二人三脚で獲得を目指す
総務省の調査によれば、全国の空き家数は900万戸、空き家率は13.8%と過去最高を記録しています。しかし、この「社会課題」は、見方を変えれば大きな「ビジネスチャンス」でもあります。特に小規模事業者や個人事業主にとって、空き家活用は初期投資を抑えながら新たな事業を始めるための絶好の機会となり得ます。
そして、その挑戦を後押しするのが、小規模事業者持続化補助金をはじめとする各種補助金制度です。適切に活用することで、改装費やプロモーション費用などの初期費用を大幅に軽減し、事業の早期軌道化が期待できます。
ただし、補助金の獲得は容易ではありません。採択されるためには、説得力のある事業計画書の作成と的確な申請手続きが不可欠です。ここに、行政書士の専門性が大きく貢献します。
行政書士しかま事務所では、空き家活用ビジネスに関する以下のサポートを提供しています
- 小規模事業者持続化補助金など各種補助金の申請支援
- 空き家活用事業に関する事業計画書作成支援
- 住宅宿泊事業法に基づく民泊届出
- 飲食店営業許可、古物商許可など各種営業許可申請
- 法人設立、個人事業開業手続き
空き家という「眠れる資源」を活かし、地域に新たな価値を生み出すビジネスは、日本社会が直面する課題解決にも貢献します。そのチャレンジを、私たち行政書士がサポートいたします。
本記事は2025年5月時点の法令・公募情報に基づいています。補助金の詳細は、必ず最新の公募要領等をご確認ください。また、本記事は一般的な情報提供を目的としており、補助金の採択を保証するものではありません。個別具体的な申請については専門家にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。03-6824-7297営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております