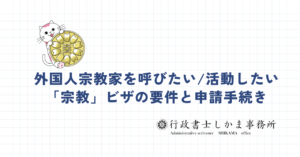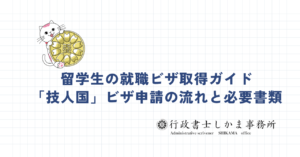グローバル企業必見!在留資格「企業内転勤」ビザの要件・手続きを専門解説 【2025年5月最新版】
1. はじめに
はじめまして。行政書士しかま事務所の行政書士です。当事務所では、在留資格申請を中心に、外国人の方々や企業の皆様のビザ関連手続きを専門的にサポートしています。
グローバル展開する企業にとって、海外拠点からの人材を日本拠点へスムーズに異動させることは、事業戦略上、極めて重要な課題です。その際に活用される在留資格「企業内転勤」は、国際的な人材活用における不可欠な経営ツールとなっています。
しかし、この在留資格の取得には特有の厳格な要件が存在し、十分な理解と準備なくしては申請が不許可となるリスクもあります。さらに2024年の入管法改正では「企業内転勤2号」が新設されることが決まり、2027年またはそれ以前に施行される予定です。
本記事では、行政書士として多くの申請をサポートしてきた経験をもとに、「企業内転勤」ビザについて専門的視点から詳細に解説します。2025年5月時点の最新情報と審査傾向をお伝えします。
この記事でわかること
- 在留資格「企業内転勤」の制度趣旨と対象活動
- 取得のための厳格な要件(転勤直前の継続勤務期間、職務内容、企業関係性など)
- 申請プロセスと必要書類
- 不許可となりやすいケースと対策
- 2024年法改正で新設された「企業内転勤2号」の概要と要件
2. 在留資格「企業内転勤」とは?
制度趣旨と位置づけ
在留資格「企業内転勤」は、日本の公私の機関(受入機関)が、外国の事業所(転勤元)に所属する従業員を、期間を定めて日本に受け入れ、特定の業務に従事させるための在留資格です。出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく就労資格の一つとして位置づけられています。
重要なのは「期間を定めて」という点です。企業内転勤ビザは、一定期間、日本法人で勤務することを目的とした在留資格であるため、転勤の期間が明確に定められていない場合、在留資格の該当性が認められず、許可が下りません。
ポイント
転勤申請書や雇用契約書の就労予定期間に「定めなし」や「無期限」などの表記をすると、不許可となる可能性が高くなります。入国管理局の審査では、転勤が一時的なものであり、一定期間後に本国の企業に戻ることが前提とされているかどうかが重視されます。
対象となる活動内容
この在留資格で認められる活動内容には、明確な制限があります。特に重要なのは、日本で行う活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するものである必要がある点です。具体的には以下のような業務が該当します
- 技術分野:システム開発、プログラミング、エンジニアリング、製品設計など
- 人文知識分野:経営企画、人事・総務、法務、財務・会計、マーケティングなど
- 国際業務分野:海外営業、通訳・翻訳、国際取引など
重要な注意点
製造ラインでの現場作業や単純労働は「技術・人文知識・国際業務」に該当せず、企業内転勤1号ビザでは認められません。これが2024年法改正で新設される「企業内転勤2号」で緩和される見通しです(詳細は後述)。
「転勤」の概念
企業内転勤ビザは、あくまで同一企業グループ内(または密接な関連企業間)での異動を前提としています。新規採用とは明確に区別されており、転勤元での一定期間の勤務実績が必須となります。この「転勤」という概念は、本制度の根幹をなす重要な要素です。
在留期間
企業内転勤ビザの在留期間は、「5年」「3年」「1年」または「3ヶ月」のいずれかです。実際にどの期間が許可されるかは、申請者や企業の状況、提出書類の内容などにより決定されます。現在の審査傾向では、初回申請では比較的短めの期間が付与され、更新とともに長くなるケースが多く見られます。
3. 「企業内転勤」ビザ取得のための厳格な要件
① 申請人(転勤する従業員)に関する要件
【最重要】転勤直前の継続勤務期間
申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において継続して1年以上、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事しながら勤務している必要があります。この「継続して1年以上」の勤務期間の立証は、申請の成否を左右する極めて重要なポイントです。
実務上の重要ポイント
企業内転勤ビザの審査では、この1年以上の勤務要件が厳格に審査されます。一度退職した方を転勤直前に再雇用し、企業内転勤ビザを申請することは認められません。ただし、過去1年間に日本に転勤していた外国人が一度帰国し、再び日本に転勤する場合、その日本での勤務期間も1年以上の勤務要件としてカウントすることができます。
「継続して1年以上」の証明には、以下の書類が重要となります
- 転勤元企業が発行する在職証明書(勤務開始日、継続期間、職務内容を明記)
- 給与支払証明書や社会保険料納付証明書などの補強資料
- 職務経歴書(詳細な業務内容と期間を記載)
日本での職務内容
日本の受入機関で従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることが必要です。具体的かつ詳細な職務内容を示し、専門的・技術的分野での業務であることを明確に説明できなければなりません。
実務上の重要ポイント
転勤前と転勤後の具体的な職務内容に直接的な関連性がある必要はありません。つまり、転勤前の業務と転勤後の業務が異なっていても、それぞれが「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば問題なく許可されます。
報酬要件
日本人が同等の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。この「同等額以上」の基準は、単に最低賃金を上回れば良いというものではなく、同職種・同職位の日本人従業員との比較において判断されます。
実務上の重要ポイント
一般的に、実務上の最低基準として「月額20万円前後」が目安とされていますが、この金額が各都道府県の最低賃金を下回る場合は許可されません。また、本国から給与が支給される場合、申請時の為替レートによって日本円換算した際に、基準額を下回らないよう注意が必要です。
② 転勤元と転勤先の企業関係性
企業内転勤が認められるのは、特定の関係性がある企業間のみです。単なる取引先や業務提携先からの転勤は認められません。
転勤が認められる企業間関係の例
- 本店・支店間の転勤
- 親会社・子会社間の転勤(議決権の50%超を保有するなど)
- 子会社間の転勤(同一の親会社を持つ関係)
- 関連会社間の転勤(議決権の20%以上50%以下を保有するなど、一定の継続的関係性がある場合)
注意点
単に同じ経営者(社長)が本国と日本の会社を所有しているだけでは、企業内転勤ビザの対象とは認められません。明確な資本関係や業務提携があることを示す書類の提出が必須です。また、企業内転勤ビザの現在の審査傾向では、孫会社同士の関係性(例:A社の子会社B社の子会社C社から、A社の子会社D社への転勤)は直接的な資本関係がなく、認められないことが多いので注意が必要です。
企業間関係性の証明には、以下の書類が必要です
- 登記簿謄本
- 株主名簿
- 有価証券報告書
- 会社案内
- 取引実績を示す資料
- 組織図(グループ企業の関係を示すもの)
③ 受入れ機関(日本の事業所)に関する要件
日本の受入れ機関にも、以下のような要件があります
- 日本において事業が適正に行われ、安定性・継続性が認められること(決算状況などが審査される)
- 転勤者を受け入れるための事業所(オフィス等)が確保されていること
- 転勤者が従事する業務の実施体制が整っていること
特に、日本の受入れ機関の経営状況(赤字決算や債務超過など)は、審査において厳しくチェックされる要素です。経営状況に不安がある場合は、事業の将来性や安定性を示す補足資料の提出が重要となります。
4. 申請プロセス(招聘・変更の一般的な流れ)
海外から招聘する場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外にいる従業員を日本へ転勤させる場合、まず日本の受入れ機関が「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)」の交付申請を行います。
- 日本の受入れ機関(申請取次行政書士)が、転勤者の代理として管轄の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
- 審査期間(目安:1〜3ヶ月程度)を経て、認定証明書が交付される
- 交付された認定証明書を転勤者へ送付
- 転勤者が自国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請
- 査証発給後、日本へ入国
- 入国時に在留カードが交付される
企業内転勤ビザの審査期間
企業内転勤ビザの審査期間は通常1~3ヶ月程度ですが、審査状況や提出書類の内容によって変動することがあります。特に、企業間の関係性や転勤者の勤務実績を示す書類に不備がある場合は、追加資料の提出を求められ、審査期間が長引く場合があります。
国内で変更・更新する場合
すでに日本に在留している外国人が、他の在留資格から「企業内転勤」への変更を希望する場合や、「企業内転勤」の在留期間を更新する場合、以下のプロセスとなります
- 本人または代理人(申請取次行政書士)が管轄の地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う
- 審査期間(目安:2週間〜2ヶ月程度)を経て、結果が通知される
- 許可の場合、新しい在留カードが交付される
更新申請時の注意点
更新申請時には、申請人の住民税や社会保険料の納付状況が厳しくチェックされるため、これらが未納の場合には更新が認められない可能性があります。また、転勤期間の延長理由や業務の継続性についても詳細な説明が求められます。
5. 主な必要書類リスト
「企業内転勤」ビザの申請には、多くの書類が必要です。以下は一般的な必要書類ですが、個別ケースや管轄の出入国在留管理局により、追加書類を求められる場合があります。
基本書類
- 申請書(該当するもの)
- 申請人の写真(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影したもの)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し(国内申請の場合)
申請人の要件証明
- 転勤元機関発行の在職証明書(勤続1年以上と詳細な職務内容を記載したもの)
- 最終学歴証明書(卒業証書または学位証明書とその日本語訳)
- 職務経歴書(詳細な業務内容と期間を記載)
- 給与証明書(直近の給与額を証明するもの)
日本での活動・待遇証明
- 転勤命令書(辞令)
- 労働条件通知書または雇用契約書(報酬額、職務内容、期間明記)
- 日本での職務内容説明書(具体的な業務内容、必要な専門知識・技術を詳述)
- 組織図(申請人の位置づけを示すもの)
企業関係証明
- 転勤元・転勤先の関係を示す公的・私的文書
- 両社の商業登記簿謄本(現地法に基づく会社登記証明書等)
- 株主名簿
- 会社案内(パンフレット)
- 出資関係図
- 事業提携契約書(該当する場合)
受入機関証明
- 日本の受入れ機関の商業登記簿謄本
- 直近の決算報告書(損益計算書・貸借対照表)
- 事業所の賃貸契約書
- 従業員数を証明する資料(社会保険加入者一覧等)
- 会社パンフレットおよびウェブサイトの写し
重要な注意点
外国語で作成された証明書類には、原則として日本語訳の添付が必要です。また、事案や企業規模(カテゴリー)により必要書類は異なるため、入念な事前確認が必要です。出入国在留管理庁は申請書類をカテゴリー1~4に分類し、カテゴリーによって提出書類の簡素化が図られています。
6. 申請における注意点・不許可になりやすい典型例
「企業内転勤」ビザ申請で不許可となるケースには、一定のパターンがあります。以下に代表的な不許可理由と対策を解説します。
転勤直前1年以上の勤務期間の立証不備
最も頻繁に見られる不許可理由の一つです。在職証明書の内容が曖昧であったり、1年に満たない勤務期間で申請したりするケースが該当します。
対策
転勤元企業による詳細な在職証明書を準備し、可能であれば給与明細や社会保険料納付証明書などの客観的な補強資料も併せて提出しましょう。
転勤元・転勤先の企業関係性の証明不足
企業間の資本関係や組織的関連性を示す客観的証拠が不十分な場合、不許可となるリスクが高まります。
対策
登記簿謄本、株主名簿、組織図など、企業間の関係を公的に証明できる資料を複数用意しましょう。特に直接的な資本関係がない場合は、実質的な関連性を示す詳細な説明と証拠が重要です。
日本での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない
日本での職務内容が単純労働や、専門性・技術性が低いと判断される場合は不許可となります。
対策
職務内容説明書で、業務の専門性・技術性を具体的に記載し、申請人の学歴・職歴との関連性を明確に示しましょう。可能であれば、組織図や業務フロー図なども活用すると効果的です。
報酬額が日本人従業員と比較して低い
提示される報酬額が同等職種の日本人従業員と比較して著しく低い場合、不許可となる可能性があります。
対策
同職種・同職位の日本人従業員の給与水準を示す資料や、業界の標準的な給与水準に関する資料を準備しましょう。また、住宅手当や通勤手当などの各種手当も含めた総支給額で比較することも有効です。
日本国内の別会社への派遣を予定している
企業内転勤ビザでは、日本国内の別会社への派遣は原則として認められていません。
対策
派遣業務を予定している場合は、企業内転勤ビザではなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するのが適切です。派遣を行う場合は労働者派遣法に基づく適正な契約が求められます。
受入れ機関の経営状況に不安がある
日本の受入れ機関が赤字決算や債務超過など、経営状況に不安がある場合、安定的な雇用が確保できるか疑問視されます。
対策
直近の売上増加傾向や今後の事業計画など、経営改善の見込みを示す補足資料を提出しましょう。場合によっては、親会社からの財政的支援を示す文書なども効果的です。
申請書類間の不整合、説明不足
提出した各種書類の内容に矛盾がある場合や、重要なポイントの説明が不足している場合も不許可リスクが高まります。
対策
申請前に全書類の内容を相互チェックし、矛盾点がないか確認しましょう。不明確な点は、補足説明資料を追加することで、審査官の疑問を解消できる可能性が高まります。
転勤期間が明確でない
「期間が定まっていない転勤」は在留資格該当性が認められないため、転勤期間を明確に定めていないケースでは不許可となります。
対策
転勤申請書や雇用契約書には、具体的な転勤期間(例:「3年間の予定で日本で勤務し、期間終了後は本国の本社へ帰任する予定」)を明記しましょう。
審査動向
出入国在留管理庁は審査の厳格化を進めており、特に企業間の関係性や転勤者の勤務実績、日本での業務内容についてより詳細な資料を求める傾向が強まっています。必要書類の準備は早めに行い、不備のない状態で申請することが重要です。
7. 2024年法改正で新設:企業内転勤2号について
2024年6月、入管法の改正により、「企業内転勤2号」ビザが新設されることが決まりました。この新しい在留資格は、2027年またはそれ以前に施行される予定です。
企業内転勤2号とは
「企業内転勤2号」は、技能等を修得するために日本に転勤し、講習を受けながら業務に従事する外国人のための在留資格です。現行の「企業内転勤1号」ビザとは異なり、より幅広い業務内容に対応することが可能となります。
企業内転勤1号と2号の主な違い
| 項目 | 企業内転勤1号 | 企業内転勤2号 |
|---|---|---|
| 業務内容 | 技術・人文知識・国際業務に該当する業務のみ(専門的業務) | 現場作業を含む幅広い業務が可能(単純労働も含む) |
| 在留期間 | 最長5年(更新可能) | 通算1年程度(予定) |
| 目的 | 業務遂行 | 技能等の修得(講習受講が必須) |
| 受入企業の要件 | 一般的な要件 | より厳格(常勤職員20人以上、受入人数は常勤職員の5%以内など) |
企業内転勤2号の主な要件(現時点での検討内容)
厚生労働省の有識者会議での検討内容によると、以下のような要件が想定されています
① 受入れ機関の規模・受入れ体制の要件
- 受入れ企業(日本の事業所)の常勤職員が20人以上であること
- 受入れ人数枠は受入れ企業の常勤職員数の5%までとすること
② 在留期間
- 企業内転勤2号での在留は、通算して1年までとすること
③ 受け入れる外国人に関する要件
- 送出元(転勤元)において1年以上勤務していること
- 日本人と同等以上の報酬を受けること
企業内転勤2号の位置づけ
企業内転勤2号は、技能実習制度の企業単独型において技能移転による国際貢献という制度目的に合致して適正な受入れを行っていた受入れ機関を対象としています。研修要素を含みつつも、単に労働力として扱うのではなく、適正な技能移転を行うことが前提とされています。
施行時期
企業内転勤2号ビザは、「育成就労制度」の創設とともに施行される予定で、改正法の公布日(2024年6月21日)から起算して3年以内、つまり最長で2027年6月頃までに施行されることが予定されています。ただし、それ以前に施行される可能性もあります。
注意点
企業内転勤2号の詳細な要件や手続きについては、今後法務省令で定められる予定です。最新情報を随時確認することをお勧めします。
8. まとめ
在留資格「企業内転勤」は、グローバル企業が海外人材を日本で活用するための重要な制度ですが、その取得には厳格な要件と綿密な準備が必要です。
本記事で解説したように、特に「転勤前1年以上の継続勤務」「企業間の関連性」「日本での職務内容(技人国該当性)」「報酬額」「受入企業の安定性」は厳格に審査されるポイントです。これらの要件を満たさない場合、不許可となるリスクが高まります。
また、2024年の入管法改正で新設された「企業内転勤2号」は、より幅広い業務での受入れを可能とする制度ですが、受入れ体制や目的などに一定の制限が設けられる見通しです。
成功するための鍵は、事前の要件確認と、不備のない書類準備にあります。特に以下の点に留意しましょう
- 転勤元での1年以上の勤務実績を客観的に証明できる資料の準備
- 企業間の関係性を明確に示す公的書類の用意
- 日本での業務内容の専門性・技術性を具体的に説明する資料の作成
- 同等の日本人従業員と比較して遜色ない報酬額の設定
- 受入企業の安定性・継続性を示す財務資料の準備
- 転勤期間を明確に定め、一時的な転勤であることの説明
これらのポイントを踏まえた上で、書類作成・申請手続きを進めることで、スムーズな「企業内転勤」ビザの取得が期待できます。また、「企業内転勤2号」の導入に関しては、最新の情報を随時確認することをお勧めします。
9. 専門家へのご相談
在留資格「企業内転勤」の申請は、複雑な企業間関係の立証、職務内容の適切な説明、多数の必要書類の準備・作成など、専門的な知見が求められる場面が多くあります。
行政書士しかま事務所では、企業内転勤ビザ申請に関する豊富な経験と専門知識に基づき、以下のサポートを提供しています
- 企業の状況に応じた最適な申請戦略の立案
- 必要書類の作成支援と内容チェック
- 申請取次(可能な場合)
- 不許可リスクの事前診断と対策提案
- 転勤後のビザ更新や家族の呼び寄せに関するサポート
- 企業内転勤2号を含む最新制度の情報提供とアドバイス
グローバル人材の活用に関するお悩みやご質問がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回相談は無料で承っております。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的なケースについては専門家への相談をおすすめします。記事内容は執筆時点(2025年5月)での法令に基づいており、最新の法改正を反映していない場合があります。
お気軽にお問い合わせください。03-6824-7297営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら オンライン相談も承っております